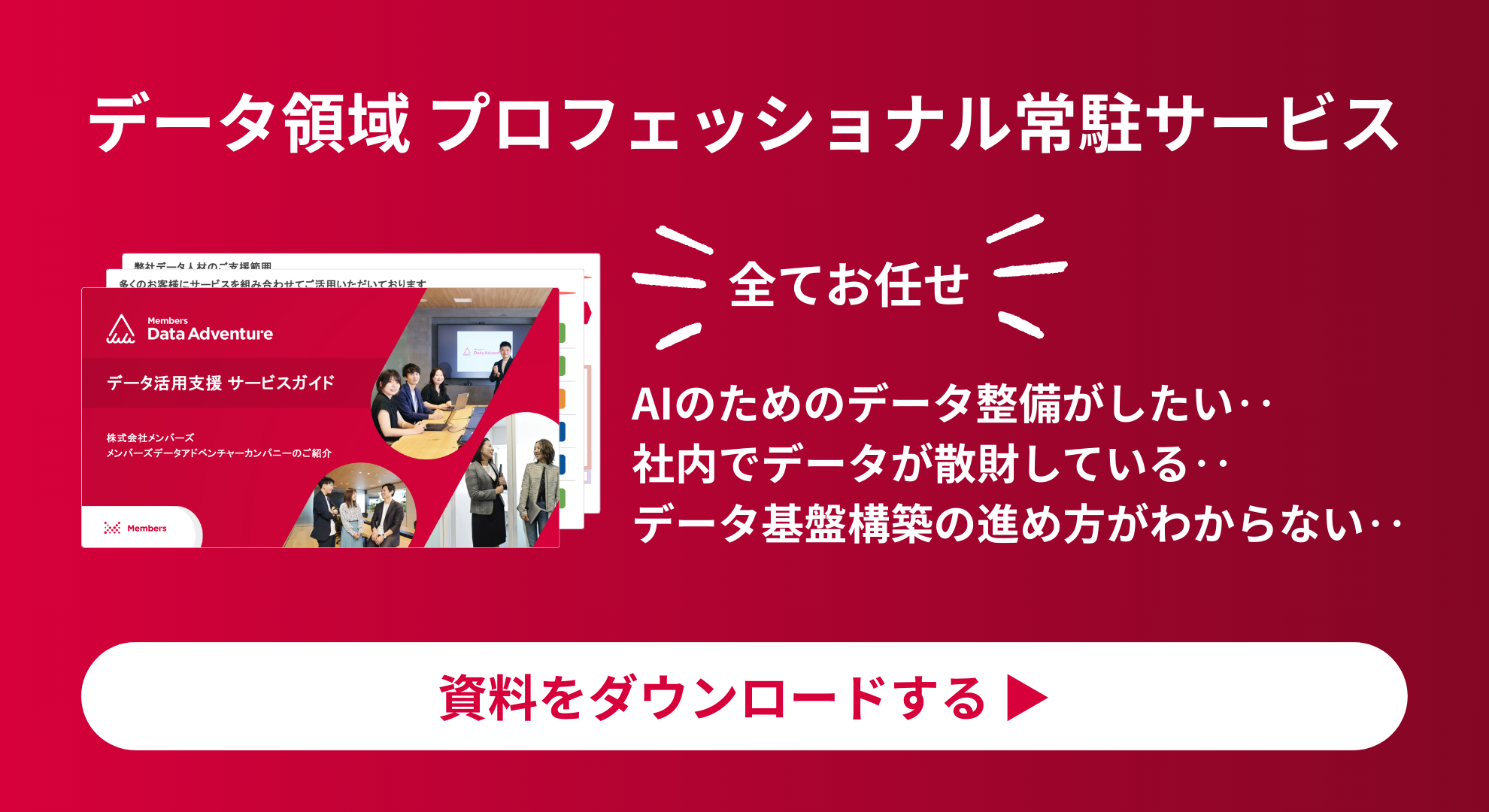情報の一元化とは?脱サイロ化で組織のデータ活用を加速させる方法を解説
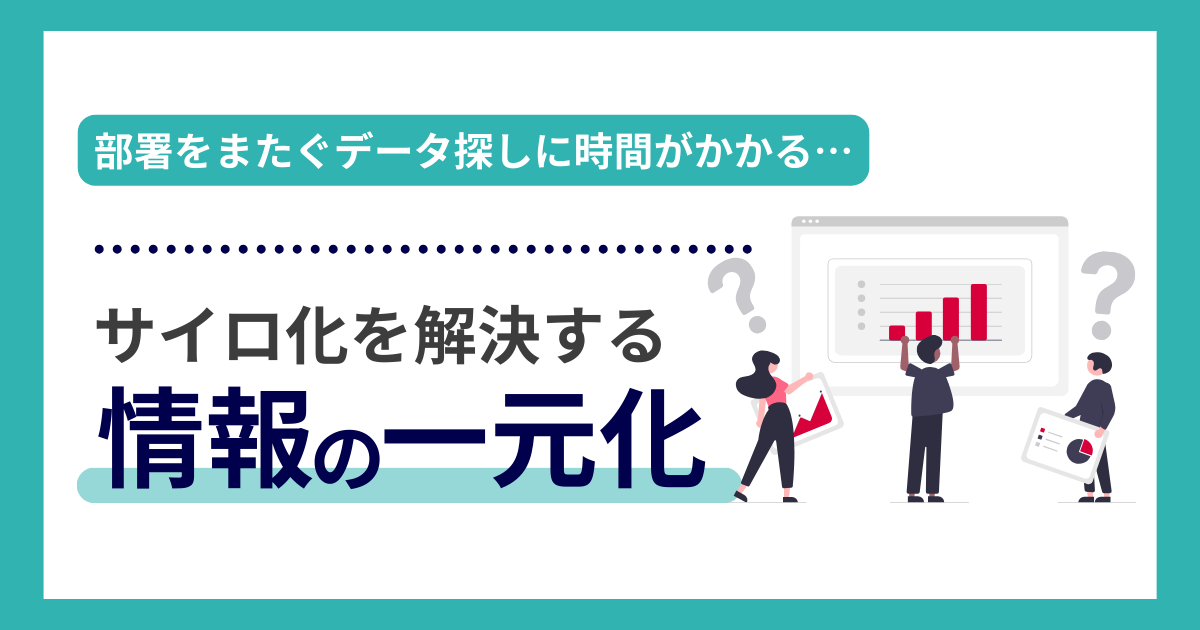
部門ごとに情報が分断され、必要なデータがすぐに見つからない。そんな「情報のサイロ化」は、今や多くの企業で深刻な課題です。この記事では、データの利活用をどのように加速させていくのかを、情報の一元化という観点からお伝えします。データの利活用においては、ただデータを用意し分析するだけではなく、活用しやすい環境を整備することも重要な要素です。
▶目次
多くの企業がDXを掲げる一方、「データをどう事業成果に繋げるか」という最も重要な壁に直面しています。データ基盤を整えても、そこからビジネス価値を生み出せなければ意味がありません。
弊社は、データ領域のプロフェッショナル人材の提供により、お客さまのステージに合ったデータ活用~定着を継続的に支援します。
関連資料:DX×データ活用で組織と事業を推進!
01. 情報のサイロ化と一元化とは?
01-1. 情報のサイロ化の定義と具体例
情報のサイロ化とは、組織内の各部門やチームが持っているデータが他部門と共有されていない状態を指します。例えば以下のようなケースでは情報のサイロ化が発生しているといえます。
- ・営業部門が持っている顧客情報をマーケティング部門が把握・アクセスできていない。
- ・データに関する仕様をシステム部門のみが把握しており、実際にデータを活用するユーザー部門がデータを理解するのに時間がかかってしまう。
01-2. 組織における情報のサイロ化の弊害
このような情報のサイロ化は、知っていれば未然に防げたトラブルによって手戻りが発生してしまったり、社内での情報収集に時間がかかってしまったりなど、業務効率の低下につながります。業務効率の低下はそのままプロジェクトの進捗や意思決定を遅らせてしまい、ビジネスへの悪影響を及ぼします。
また、データ活用においても、情報のサイロ化は以下のような理由から障壁となってしまいます。
- ・そもそもどのようなデータがどこにあるかがわからず収集に時間がかかってしまう。
- ・収集されたデータがどのような仕様なのかの解析にも時間がかかる。
- ・データの管理方法がバラバラなため、データを利用するための連携に都度大きな工数がかかってしまう。
01-3. なぜ情報のサイロ化が起きるのか
情報のサイロ化が起きてしまう要因としては、主に組織構造によるものとシステム設計によるものの2つが挙げられます。
- ・組織構造によるもの
部門間で連携がうまく取れていないと情報のサイロ化が発生しやすくなります。
これは縦割り組織のような構造の中で連携がうまく取れていないケースや、「この部門にお願いしてもきちんと対応してくれない」など部門間の関係性に起因する場合もあります。
- ・システム設計によるもの
各部門が別々のシステムを導入している場合、それらのシステムは各部門に最適化されています。
これによりデータ自体も各部門およびシステム向けにカスタマイズされていることが多く、仕様もバラバラとなり共有することが難しくなってしまいます。
01-4. 情報の一元化とは?
組織の情報を部門やチームを問わず、1箇所に集約・管理する「情報の一元化」を行うことで、これらの課題を解決することが可能です。
情報の一元化とは、全員が同じ場所から同じ情報を利用できるようにすることを指します。これにより組織内での情報の所在が明確になり、サイロ化の防止、業務効率化やデータ利活用の促進につながります。
02. 情報の一元化で得られるメリット
02-1. 脱サイロ化による部門間連携の強化
情報の一元化を行うと、各部門が同じ情報を通じて業務を進められるため、認識齟齬やそれによる手戻りが減少します。共通認識のもと迅速な協働が可能になり、部門間のコミュニケーションの促進も期待できます。
例えば営業、マーケティング、商品開発の部署がリアルタイムに顧客情報を共有することでサービス品質の向上がスムーズに行われるようになります。複数の部門を横断したプロジェクトにおいても情報が1箇所に集約されるため連携体制が強固になり、プロジェクトの成功に大きく貢献します。
02-2. 情報共有のスピードアップと質向上
情報源が一つに集約されていることで、必要な情報の所在が明確になり、情報探しや確認作業にかかる時間が削減されます。また、一元管理された情報に対して責任を明確化し、定期的にメンテナンスすることで、常に最新かつ正確な情報が共有されるようになります。これにより、古い情報や誤った情報による混乱を防止できます。従来は情報を更新した後、各部門へ展開・共有する手間がありましたが、今後は所定の箇所を更新するだけで済むようになり、メンテナンス負担の軽減も期待できます。
02-3. データ活用による意思決定の迅速化と高度化
情報の一元化により、部門をまたいだ多角的なデータ分析が可能となります。営業成績・顧客動向・市場データなどを統合し、可視化することでトレンドや課題の早期発見につながり迅速な対応が可能となります。
従来のように情報がサイロ化されていると、各部門からの情報取得に時間がかかり、総合的な判断が難しい状況に陥りがちでしたが、一元化によりそれが解消され、迅速かつ精度の高い意思決定が実現します。
さらに分析するデータそのものに加え、データの使用や分析におけるナレッジも一元化することでデータ分析自体の高度化にもつながります。
03. 一元化すべきデータ、すべきでないデータ
03-1. 一元化すべきデータ
情報の一元化は業務効率化や意思決定の迅速化にとても有効である一方、すべてのデータを一元化すればよいというわけではありません。ここではまず一元化すべきデータについてご説明します。
- 意思決定に関わるデータ
経営層や管理職など、複数部門にまたがる関係者が参照する必要があるため、一元化するメリットが大きいデータです。個別管理による重複や齟齬の発生を防ぐことができます。顧客情報、製品仕様、KPI、予算、実績データなどがこれに該当します。
ただし、各事業部ごとに売上データの閲覧範囲の制限が必要な場合もあるため、必要に応じてアクセス権による制御が求められるケースも存在します。 - ナレッジやドキュメント
これらの情報を一元化することで再利用性や学習効果を高め、全社的な業務効率化につながります。マニュアルや社内規定、QAなどがこれに該当します。
03-2. 一元化すべきでないデータ
一方で以下のような個人的なデータや、秘匿性の高いデータは一元化すべきではないものとして挙げられます。
- 個人のメモや一時的な作業用ファイル
これらのデータを一元化に含めてしまうとノイズが増え、情報の検索性が低下してしまう恐れがあります。下書きメモや個人のTODO、個人用に作成したテーブルなどがこれに該当します。 - プライバシー保護の観点から機密性の高いデータ
限られた人しか閲覧すべきでない情報や、漏洩リスクの高いデータの一元化には慎重さが必要です。一元化する場合は厳格なアクセス権の設計が不可欠です。人事評価、給与情報、顧客の個人情報などが該当します。 - 法的に公開してはいけないデータ
法令や契約上の制約により、社内全体で共有できないデータも存在します。このようなデータは一元化せず、限られた範囲での管理が求められます。顧客との契約情報や法務対応に関する文書などがこれに該当します。
03-3. データ特性に応じた管理方法
一元化を進める際は、データの特性に応じた適切な管理が不可欠です。
社内で広く共有すべき情報がある一方で、機密性の高い情報や法的制約のある情報も存在するため、アクセス権の設計が重要なポイントになります。これにより情報の一元化のメリットを享受しつつ情報公開によるリスクを最小限に抑えることが可能です。
04. 情報の一元化を実現するためのステップ
04-1. 具体的な手順
ここでは、情報の一元化によってデータの利活用を促進するためのアプローチについて解説します。
一元化には主に以下の3ステップでの段階的な進め方が効果的です。
- 現状把握と方針の明確化
まず、各部署で扱っているデータについての棚卸を行い、「どのデータが、どこに、どのような形式で存在しているのか」を整理します。複数の部門での利用や重複を確認するとともに、データの用途や分析目的を明確化しましょう。各部門の主要KPIや分析の切り口(部門別、取引先別など)を明確化すると、今後の設計がスムーズになります。 - ツール選定と基盤構築
次に情報を一元管理・共有するためのツールを選定し、データを集約する基盤を構築します。
ステップ1で策定した方針に沿って、ツールを選定しましょう。様々なデータソースから取得したデータを1箇所に集約し、分析用途のデータは、このタイミングで最低限のデータクレンジング(欠損値の補完や単位や型の統一)を行うと、その後の広い活用に効果的です。可視化ツールも統一することで、組織全体で同じ指標に基づいて意思決定を行えるようになります。更新頻度やアクセス権限などの運用ルールについても併せて整備します。 - PDCAを回す
最後に、継続的な活用と改善サイクルを構築します。
まずは、一部の部門からスモールスタートを行うなどして、利用状況の確認や利用者からのフィードバックをもらいましょう。そこで得られた課題を改善するとともに徐々に組織全体に拡大させることで一元化を進めましょう。一度一元化をしたら終わりではなく、データの管理方法や運用ルールの見直しを継続的に実施することで情報の一元化の恩恵を最大限に活かすことができます。
04-2. ツール選定のポイント
- データの統合のしやすさ
様々なデータソース(CRMシステム、MAツール、データベース、ドキュメント)と連携ができるかどうかは、ツール選びで重要なポイントとなります。複数の部門で分断されているデータの一元化には、柔軟な接続性が求められます。 - スケーラビリティ
現時点のデータ量だけでなく、今後の拡張にも対応できるかを見極めましょう。特に大量データを扱う場合には、クラウド型のデータウェアハウス(例:BigQuery、Snowflakeなど)の活用が効果的です。自動でリソースを拡張でき、パフォーマンスの低下を防げます。 - アクセス制御とセキュリティ
誰がどのデータにアクセス・編集できるかを細かく管理できる機能が必須です。アクセスログの取得やデータの暗号化に加え、社内の認証基盤と連携したSSO(シングルサインオン)対応も重要な検討要素となります。 - 操作性・使いやすさ
情報の一元化は全社的な活用を前提とするため、直感的に操作できるかどうか、学習コストが低いかといった視点も重要です。高機能なツールであっても、現場で使われなければ意味がありません。自社のリテラシーレベルに合ったツールを選ぶことが成功の鍵です。 - コストおよび導入・運用負荷
初期導入にかかる費用や運用コスト(月額課金やユーザー数や処理スペックによる従量課金などの価格体系)が適正かどうかも重要なポイントです。一元化されたデータの管理を社内で行うのか社外に依頼するかも判断が必要になる場合があります。費用対効果を意識して取り組まなければ継続的な取り組みが行えなくなってしまうというリスクがあるのでしっかりと確認しましょう。
05. 弊社における情報の一元化の取り組み事例
05-1. 【食品業界】複数事業会社におけるデータマネジメントの一元化支援
- ・課題:複数の事業会社や販売チャネルが存在し、データ基盤への連携フローやデータのフォーマットがバラバラのため一元管理やセキュリティリスクの検知に負担が大きかった。
- ・施策:データレビューの仕組みを策定し、様々なデータに対して統一的なチェック体制を導入。
- ・成果:レビュー結果をもとにしたデータ品質の担保やデータカバナンスの向上を実現した。
05-2. 【アパレル業界】データを一元化し顧客ニーズの把握が可能に
- ・課題:社内にデータが散在していたため、顧客ニーズを深く理解することができない状態だった。
- ・施策:社内のデータを一元化し、組み合わせることで顧客ニーズの可視化を行った。
- ・成果:これまで得られなかった顧客ニーズを把握することでマーケティング施策への活用が行えるようになった。
【プレスリリース】データ活用における生成AI導入・活用支援サービスを提供開始 データ抽出・集計・本番移行の作業時間を8割削減

弊社にて、SQLによるデータ抽出・集計・本番移行作業に生成AIを導入したところ、一連の作業にかかる時間が月120時間から月24時間にまで短縮され、作業時間を8割削減できたという結果が出ています。
サービスの提供を通じて、企業のデータ活用における業務効率化と高度化、内製化の実現に向けた支援を加速させていきます。
プレスリリースの詳細についてはこちらから
まとめ
この記事では、データの利活用を加速させる手段として「情報の一元化」について解説しました。情報のサイロ化は、組織内のデータが部門間で共有されず、業務効率や意思決定に悪影響を及ぼします。社内でのデータ活用をより促進していく環境を整えるために、情報の一元化は効果的な手段となりえます。一元化により、部門間連携が強化され、情報共有のスピードと質が向上し、迅速かつ高度な意思決定が可能になります。顧客情報や製品情報など一元化すべきデータがある一方で、個人情報や機密情報は慎重に扱う必要があります。現状把握、ツール選定、PDCAサイクルの確立を行うことで情報の一元化を実現し、組織の全体の業務効率化だけではなくデータの活用を通して高度な意思決定ができれば大きな成果となるでしょう。
\ データ活用についてのご相談はメンバーズデータアドベンチャーまで /
\ 相談する前に資料を見たいという方はこちら /
▶こちらも要チェック