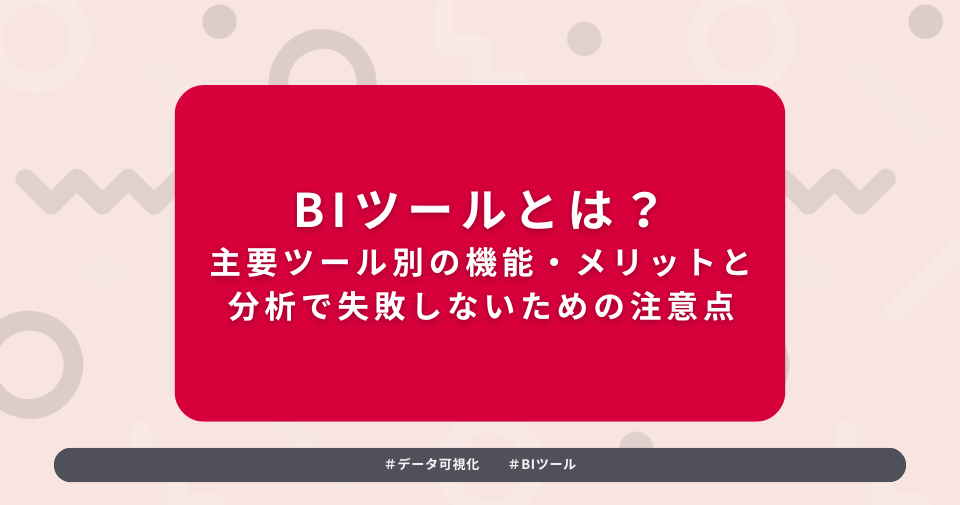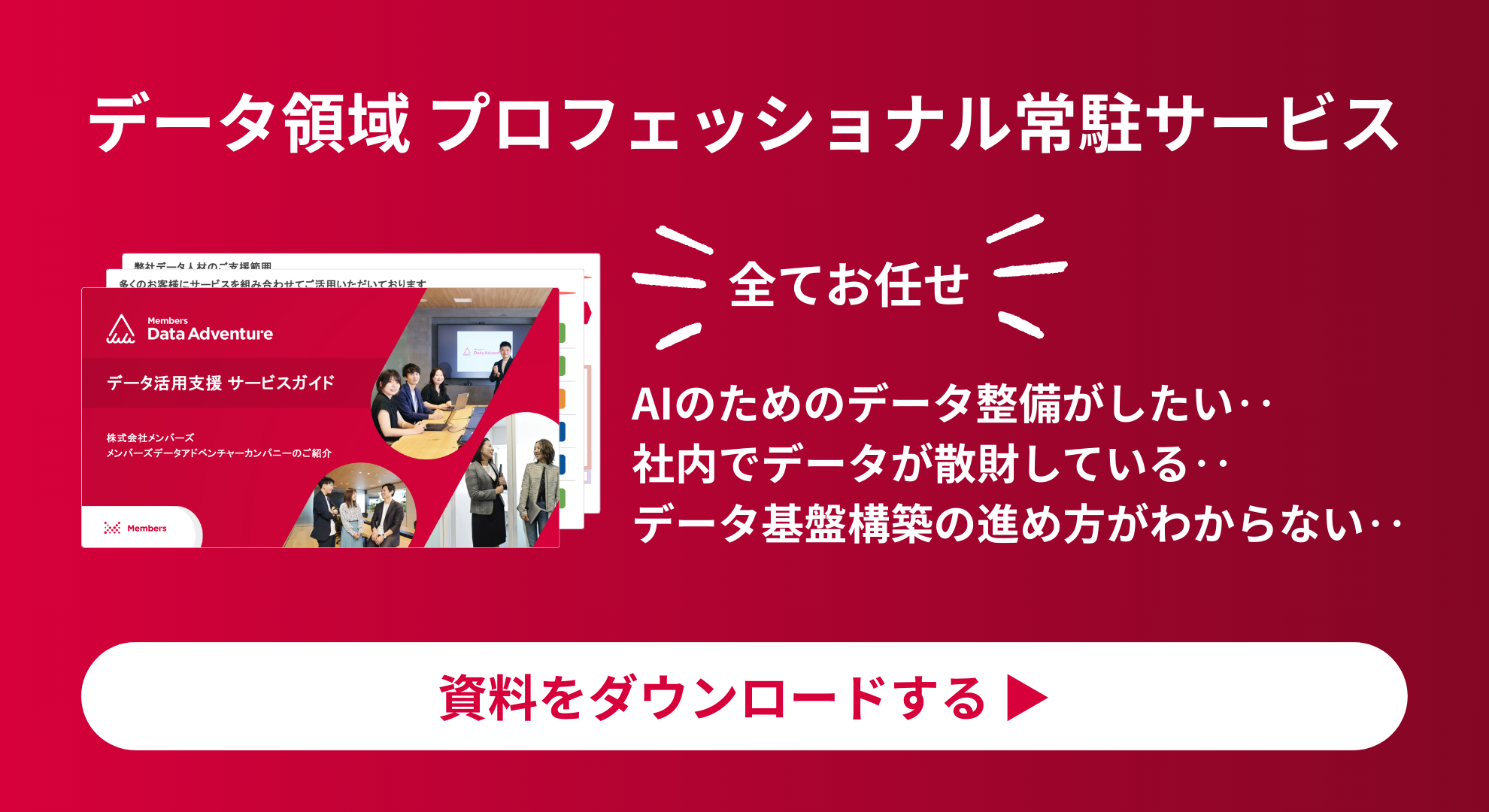ビジネスにおいてデータが重要性を増す中で、その活用はもはや選択肢ではなく必須の要素となりました。しかし、膨大なデータを前に「どう活用すればいいかわからない」「分析が難しそう」と感じている方もいるのではないでしょうか。
そんなデータ活用の課題を解決してくれるのが、Microsoftが提供するビジネスインテリジェンス(BI)ツール「Power BI」です。Power BIは、複雑なデータを直感的かつ効率的に可視化・分析できる点が大きな魅力で、企業における意思決定を強力にサポートします。
本記事では、Power BIがなぜ今これほど注目されているのか、その特徴から、表計算ソフトの定番であるExcelとの違い、具体的な活用事例までを解説します。
▶目次

開催日 2026.01.27 (火) 11:00~12:00
AI導入でROIを生み出したいマネージャー・リーダー層や社内推進担当者必見。他社事例やトレンドを交え、業務実装のポイントを解説します。
01. Power BIとは?MicrosoftのBIツール
1-1. Power BIの基本と特徴
Power BIとは、Microsoftが提供するビジネスインテリジェンス(BI)ツールであり、企業のデータ活用とDX推進を強力に支援するものです。BIツールとは、企業の様々なデータを収集・分析し、その結果を可視化することで、経営戦略や業務改善の意思決定を助けるソフトウェアを指します。Power BIはデータを収集・統合・可視化し、業務上の意思決定を支援するための有用なツールとして、近年多くの企業で利用されています。また、直感的な操作性も特徴で、専門家でなくともデータの力を活用できる点が多くの企業に評価されています。
BIツールについて詳しくはこちらで解説しています。
1-2. Power BIとExcelの違い
データ分析ツールとして広く使われているExcelとPower BIは、一見似ているように見えますが、それぞれ異なる強みを持つツールです。
- Excelは、表計算ソフトウェアとして、個別のデータの入力や管理、そして小規模なデータの集計や分析において非常に強力なツールです。手軽にグラフを作成したり、シンプルな計算を行うのに適しています。
- Power BIは、大規模データの分析や可視化に特化しています。数百万行、数千万行といった膨大なデータを高速に処理し、複雑な関係性を持つデータセットから洞察を導き出す能力に優れています。
特に、常に更新されるリアルタイムデータとの連携や、過去のデータから未来を予測する高度な予測分析において、Power BIの強力な機能は真価を発揮します。
| 機能 | Power BI | Excel |
|---|---|---|
| 主な用途 | 大規模データの分析、対話的なレポート作成 | 表計算、データ入力、小規模なデータ分析 |
| データ処理量 | 数百万行以上の大規模データに対応 | 最大約104万行 |
| データ接続性 | 100種類以上の多様なデータソースに接続可能 | 主にファイルベースのデータ(CSV, XLSXなど) |
| 可視化機能 | 高度でインタラクティブなグラフや地図を多数搭載 | 基本的なグラフが中心 |
| 共有・共同作業 | クラウド上で安全にレポートを共有、権限設定も可能 | ファイルの送受信が主体で、同時編集に制約あり |
| 学習コスト | データモデリングなど専門的な知識が必要な場合がある | 多くの人にとって馴染み深く、学習が容易 |
これら二つのツールは競合するものではなく、それぞれの得意分野を活かし、補完的に利用することで、データ活用の可能性を最大限に引き出すことができます。
02. Power BIで実現できること
Power BIは単なるグラフ作成ツールではありません。社内に散在する多種多様なデータを一つに繋ぎ、専門家でなくとも直感的な操作でその価値を引き出すことが可能です。
ここでは、Power BIが持つ以下の4つの強力な機能が、具体的にどのようにビジネスのデータ活用やDX(デジタルトランスフォーメーション)を加速させるのかを解説していきます。
- ・データ連携
- ・可視化
- ・高度な分析
- ・共有と共同作業
2-1. 多様なデータ連携
Power BIは、社内外のさまざまなデータソースと容易に接続できる柔軟なBIツールです。ExcelやCSVファイルはもちろんのこと、SQL ServerやOracleなどのリレーショナルデータベース、Google AnalyticsやSalesforceなどのクラウドサービスにも対応しています。また、社内外の分散したデータを一元的に集約し、分析基盤を構築することができます。例えば、マーケティング部門が管理するWeb広告の成果データと、営業部門が持つ顧客管理システム (CRM)の受注データを連携させることが可能です。これにより、「どの広告から流入した顧客が最も成約に至りやすいか」といった、部門を横断した分析が実現します。
このように、サイロ化しがちなデータを統合することで、全社横断的なデータ分析が可能になります。
2-2. データの可視化
Power BIでは、複雑な数値や傾向も、直感的で分かりやすいビジュアルに変換できます。ドラッグ&ドロップ操作で、ダッシュボードやレポートをスピーディに作成でき、意思決定のスピード向上に貢献します。テンプレートや自動整列機能が豊富で、デザインセンスに自信がない人でもプロ品質のダッシュボードが作成できます。
また、フィルターやスライサー機能により、閲覧者が自分で条件を切り替えて分析可能。レポートを“読む”だけでなく、“使う”ことができます。
可視化できるグラフ例:
- ・棒グラフ、折れ線グラフ、円グラフ、散布図、ヒートマップ、ツリーマップ、ゲージチャートなど
- ・地図ベースのマッピング(都道府県別売上など地理情報の可視化)
- ・KPIカード(目標達成率などの数値サマリ)
2-3. 高度なデータ分析
Power BIは統計や予測、異常検知などの分析機能も搭載しています。ビジネス課題に応じた柔軟な分析が可能です。
主な分析機能:
- ・DAX(Data Analysis Expressions)
Excelの関数に似た構文で、複雑な売上累計、前年比、移動平均などの高度な計算式が実装できます。例えば前年同月比、RFM分析スコアの算出、カテゴリ別の割合分析などが可能です。
- ・インサイト生成機能(自動分析)
MicrosoftのAIを活用し、データの外れ値や傾向を自動で分析。どの要素が売上に影響しているかといった要因分析も可能です。
2-4. レポート共有と共同作業
作成したレポートやダッシュボードは、クラウドサービスであるPower BI Serviceを通じて、簡単に社内外の関係者と安全かつ効率的に共有できます。閲覧者はWebブラウザやモバイルアプリから、いつでもどこでもアクセス可能です。Power BIが提供する共有・運用面での強みは多岐にわたります。まず、アクセス権の細かな管理により、部署や役職に応じた閲覧制限や、特定のビジュアルのみを共有するなどの柔軟なセキュリティ設定が可能です。これにより、必要な情報が必要な人にのみ共有され、セキュリティが保たれます。Microsoft 365との連携が強化されている点も大きなメリットです。Teams、SharePoint、OneDriveといったMicrosoft 365の主要サービスとシームレスに連携するため、社内コミュニケーションの流れの中でスムーズにレポートを活用できます。これにより、情報共有の効率が大幅に向上します。
03. Power BIの主要機能とライセンス
Power BIの能力を最大限に引き出すためには、主要なツールとそれぞれの役割に応じたライセンス体系を理解することが不可欠です。 Power BIは、個人のPCで分析レポートを作成する「Desktop」、作成したレポートを組織で共有・活用するクラウド基盤「Service」、そして外出先からデータにアクセスするための「Mobile」という3つのコンポーネントが連携して機能します。
この章では、これらの主要機能と、利用目的や規模に応じた最適なライセンスの選び方について解説します。
3-1. Power BI Desktop
Power BI Desktopは、Microsoft社が提供する 無料のWindowsアプリケーション です。ユーザーは自身のローカル環境で、さまざまなデータソースからのデータ取り込み、加工、モデリング、そして可視化までを一貫して行えます。グラフやダッシュボードの設計など、Power BIレポート作成の「起点」となる重要なアプリケーションです。
例えば、ある企業のマーケティング担当者が、Excelで管理している広告費データと、ウェブサーバーにあるアクセスログデータを組み合わせてキャンペーンの効果を分析したいと考えたとします。Power BI Desktopを使えば、プログラミング不要でこれらの異なるデータを読み込み、不要な情報を取り除き、関連付けて一つの分析モデルを構築することが可能です。Power BI Desktopは、データ分析に必要なすべての機能を個人のPC環境に集約し、誰でも無料で高度なレポート作成に着手できるツールです。
3-2. Power BI Service
Power BI Serviceは、Microsoft社が提供するクラウドベースのBIサービスです。Power BI Desktopで作成したレポートを、このサービスに 公開・共有 し、 チームや組織内での共同作業 が可能になります。さらに、データの自動更新スケジュールの設定や、アクセス権限の管理といった運用・管理機能も提供しており、組織的なデータ活用には欠かせないプラットフォームとなっています。
例えば、日次で更新が必要な営業実績レポートのデータソースをService上で設定すれば、毎日決まった時間に自動でデータを最新の状態に保つことができます。さらに、Microsoft 365との連携により、作成したダッシュボードをTeamsのチャネルに埋め込むことで、チーム全員が同じデータを見ながら日々の業務を進めることが可能です。Power BI Serviceは、作成した分析レポートを単なる成果物で終わらせず、組織の意思決定プロセスに組み込むための運用基盤と言えます。
3-3. Power BI Mobile
Power BI Mobileは、スマートフォンやタブレット向けの専用アプリです。外出先からでもPower BIで作成されたレポートやダッシュボードを閲覧・操作でき、最新のデータに素早くアクセスすることが可能です。これにより、営業担当者やマネージャーなど、移動が多い職種の人が迅速な意思決定を行う場面を強力にサポートします。
3-4. ライセンスの種類と選び方
| Power BI Free | Power BI Pro | Power BI Premium (ユーザー単位) | Power BI Premium (容量単位) | |
|---|---|---|---|---|
| 月額費用(税込) | 無料 | 約2,098円/月 | 約3,598円/月 | 約542,540円/月 |
| データ容量 | 最大1GB/ユーザー | 最大10GB/ユーザー | 最大100TB(共有) | 100TB〜/容量単位(共有) |
| レポートの共有 | 不可 | 可(他Proユーザーと共有) | 可(全社レベルの共有) | 可(広範囲な共有) |
| 自動更新スケジュール | 不可 | 最大8回 / 日 | 最大48回 / 日(1時間ごと) | 最大48回 / 日(1時間ごと) |
| AI機能の利用 | 一部利用可能 | 一部利用可 | 可(高度機能・生成AI) | 可(高度機能・生成AI) |
| エンタープライズ向け機能 | なし | 一部利用可 | 可(大規模・高度な機能) | 可(大規模・マルチテナント) |
| 対象ユーザー | 個人利用者 | 中小チーム・部門 | 大規模企業・エンタープライズ | 大規模企業・エンタープライズ |
Power BI:料金プラン | Microsoft Power Platformをもとに自社作成(2025年8月時点の情報)
モデルサイズ(グラフの元となるデータの容量)にかなり違いがあったり、データが自動更新される回数などに違いがあります。Premiumライセンスの容量単位のプランに関しては作成したレポートを共有するためには別途ライセンスが必要になるため注意が必要です。また、PowerBIは無償でも利用可能となっていますが、無償で利用する場合は作成したレポートの共有ができないため個人での利用に限定されます。
04. Power BIの基本的な使い方
Power BIは、専門家でなくても直感的に扱えるよう、データ分析のプロセスが体系化されています。具体的には、以下の5つのステップで構成されています。
- データの取り込み
- 整形
- モデル作成
- レポート作成
- 共有
4-1. データを取り込む
まず最初のステップは、「データの取り込み」です。データ取り込みの基本的な手順を簡単に解説します。
Power BI Desktopの起動と「データを取得」:
Power BI Desktopを立ち上げたら、「データを取得」ボタンを探しましょう。これは初期画面に表示されるか、上部のリボンメニューにある「ホーム」タブから選択できます。ここから、取り込みたいデータソースの種類を選びます。
データソースの選択:
「データを取得」をクリックすると、Power BIがサポートしているデータソースの一覧が表示されます。「Excelブック」「テキスト/CSV」「SQL Serverデータベース」など、多様な選択肢の中から、あなたのデータが保存されている形式に合ったものを選んでください。また、複数のデータソースを同時に取り込むこともできるため、部署や業務ごとに分かれたデータを統合して分析する基盤を構築することが可能です。
4-2. データを整形する
次に行うのが、「データの整形(前処理)」です。取り込んだデータはそのままでは分析に不向きなことが多く、不要な列が含まれていたり、日付の書式が統一されていなかったり、空欄が存在したりします。そのため「データの整形」を行い分析しやすい形に整える必要があります。Power BIでは「Power Queryエディタ」を使って、不要な列の削除、データ型の変換、日付の加工、複数テーブルの結合など、柔軟に前処理を行うことができます。
例えば、売上データと商品マスタが別ファイルに分かれている場合、それらを一つの分析軸として統合したり、売上金額の形式を数値に変換して計算可能にしたりといった操作が可能です。この整形作業は、分析の正確さや信頼性を左右する重要な工程です。
4-3. データモデルを作る
Power BIにおけるデータモデルの構築とは、取り込んだ複数のテーブル間にリレーションシップ(関係性)を定義することです。これにより、一見バラバラに見えるデータも互いに関連付けられ、より複雑で柔軟な分析が可能になります。
例えば、売上データに「顧客ID」や「商品コード」が含まれている場合、これらを顧客情報が記載された「顧客マスターテーブル」や、商品の詳細情報を持つ「商品マスターテーブル」と紐づけることができます。このリレーションシップを正しく設定することで、「特定の顧客がどの商品をどれだけ購入したか」といった多角的な視点からの分析が可能になるのです。適切なリレーションシップを築くことは、データ分析の精度を飛躍的に向上させます。これにより、レポート上でスライサーを使ってデータを絞り込んだり、クロス集計で複数の要素を掛け合わせて分析したりする際の整合性が保たれます。結果として、データ全体を一貫性のあるものとして扱い、より深いインサイトを得られるようになるでしょう。
4-4. レポートを作る
Power BI Desktopでデータモデルの構築が完了したら、いよいよレポートの作成に取り掛かります。ここでは、取り込んだデータをグラフやテーブルなどのビジュアルとして配置し、視覚的に分かりやすい形にしていきます。さらに、フィルターやスライサーを活用することで、ユーザーが自由にデータを探索できるインタラクティブなレポートを作成できます。レポート作成のキャンバスは、Power BI Desktopの中央に広がる白い領域です。画面右側には「フィールド」ペインがあり、ここにはデータモデル内のすべてのテーブルと列(フィールド)が表示されています。
ビジュアルを配置する手順は非常に直感的です。まず、右側の「フィールド」ペインから、グラフに表示したいデータ(例えば「売上」や「日付」など)をレポートキャンバスにドラッグ&ドロップします。データをドロップすると、Power BIは自動的に最適なビジュアルタイプ(棒グラフやテーブルなど)を推測して表示してくれます。
もし自動選択されたビジュアルが意図したものと異なる場合でも問題ありません。画面右側にある「視覚化」ペインから、円グラフ、折れ線グラフ、テーブル、カードなど、多様なビジュアルタイプを選択し、ワンクリックで変更できます。また、この「視覚化」ペインでは、色や軸の表示、タイトルの設定など、ビジュアルの詳細な書式設定も自由に行うことができ、見栄えの良いレポートに仕上げることが可能です。
4-5. レポートを共有する
Power BI Desktopでレポートが完成したら、いよいよその成果を関係者と共有する段階です。作成したレポートは、Power BI Serviceに公開することで、Webブラウザやモバイルアプリからアクセスできるようになり、セキュアかつ広範囲に情報を共有できます。
Power BI Serviceへのレポート公開:
Power BI Desktopの上部リボンにある「ホーム」タブから「発行」ボタンをクリックします。すると、Power BI Serviceのワークスペース(レポートやダッシュボードを整理する場所)を選択する画面が表示されるので、適切なワークスペースを選んで「選択」をクリックしてください。これで、作成したレポートデータとビジュアルがPower BI Serviceにアップロードされます。公開が完了すると、Power BI Service上でレポートを開くためのリンクが表示され、すぐに共有を開始できます。
アクセス権限の設定とセキュアな共有
Power BI Serviceにレポートを公開したら、次にアクセス権限の設定を行います。これは、誰がレポートを閲覧できるかを管理する非常に重要なステップです。レポートが公開されたワークスペースの共有設定を通じて、特定のユーザーやセキュリティグループに対して閲覧権限を付与できます。例えば、部署ごとや役職ごとに閲覧制限をかけたり、特定のプロジェクトメンバーにのみアクセスを許可したりといった、きめ細やかなセキュリティ設定が可能です。これにより、機密性の高い情報を含むレポートでも、情報漏洩のリスクを抑えつつ、必要な人にだけ確実に情報を届けることができます。
05. Power BIの活用事例と課題
5-1. Power BI成功事例
スポーツ関連企業におけるTableauからのリプレイス支援事例をご紹介します。
<導入前の課題>
Tableau Desktopによるデータ可視化において、ローカルでのデータ読込や複雑な計算式、フィルタリング作業によって、業務効率が低下している状況でした。また、業務が属人化しており、特定の担当者しかデータ管理ができないという課題も抱えていました。
<実施したこと>
Power BI導入に向けたPoC(概念実証)を実施しました。既存のTableauからPower BIへ可視化レポートをリプレイスし、業務品質の改善効果を検証しました。この過程で、データマートからPower BI間のテーブル設計を見直し、計算メジャーを最適化することで、処理速度の向上を図りました。
<得られた成果>
表示まで2分以上かかっていたレポートの処理速度が数秒にまで短縮され、業務効率が大幅に改善されました。このPoCを通じて、Power BIへの全面的なリプレイスの意思決定が下され、データ活用を組織的に加速させるための大きな一歩となりました。
5-2. 導入でよくある課題と対策
Power BIは強力なツールですが、導入したからといってすぐにデータ活用が進むわけではありません。多くの企業が直面する課題を理解し、適切な対策を講じることが成功への鍵となります。
主な課題としては、以下の4点が挙げられます。
- 目的が不明確で何から手をつければ良いかわからない
- 分析以前のデータ整形・加工が難しい
- レポートが活用されず作成が目的化する
- 社内に扱える人材がいない
何から手をつけていいか分からない:
Power BIを導入したものの、膨大な機能やデータの海を前にして「何から始めればいいか分からない」と戸惑うケースは少なくありません。この課題を克服するためには、まず「何を解決したいのか」という導入目的を明確にすることが不可欠です。売上分析、顧客動向の可視化など、具体的な課題を設定し、小さな範囲からスモールスタートを切ることで、成功体験を積み重ね、徐々に活用の幅を広げていくのが効果的です。
データの整形・加工が難しい:
データが散在していたり、形式が不統一だったりすると、Power BIで分析を始める前の段階でつまづくことがあります。このデータ整形・加工作業は、Power Queryの学習で効率化できますが、専門的な知識が求められる場合も少なくありません。社内での対応が難しい場合は、外部の専門家や、データ整備から支援してくれる企業のサービスを利用することも有効な選択肢ですです。
レポート作成止まりで活用が進まない:
Power BIが「データを可視化するだけのツール」になってしまい、経営判断や業務改善に活かされないという課題もよく耳にします。これを防ぐには、経営層がデータ活用にコミットメントし、データに基づいた意思決定を組織全体で奨励するデータ文化を醸成することが重要です。
社内に使える人材がいない:
Power BIの操作やデータ分析の専門知識を持つ人材が社内に不足していることも、導入後の大きな障壁となります。解決策としては、社内向け研修を実施し、従業員のスキルアップを図ることが挙げられます。また、迅速な成果を求める場合は、データ活用人材の常駐サービスを利用することも一つの手です。専門知識を持った外部のプロが、ツールの定着からデータ活用の推進までを一貫してサポートすることで、社内の負担を減らしつつ、データ活用を加速させることができます。
06. Power BIに関するよくある質問(FAQ)
6-1. Power BIは無料でどこまで使えますか?
A. Power BI Desktopは無料で利用でき、個人でのデータ分析・レポート作成が可能です。ただし、レポートの共有や共同作業にはProライセンス以上が必要になります。
6-2. Power BIを学ぶには何から始めれば良いですか?
A. まずはPower BI Desktopをインストールし、手元のExcelデータなどで実際に操作してみましょう。Microsoft公式の学習リソースやオンラインコース、セミナーの活用も有効です。
6-3. Power BIの導入費用はどれくらいかかりますか?
A. Power BIの費用は、ライセンス費用と必要に応じて発生する初期導入支援費用の主に2つで構成されます。 ライセンス費用は、ユーザー単位で課金される「Pro」プランが中心で、2025年10月現在1ユーザーあたり月額約2,098円となります。
これに加えて、データ基盤の設計、既存システムとの連携、初期レポートの作成などを外部の専門企業に依頼する場合、その規模や複雑さに応じて数十万円から数百万円の導入費用が別途必要になるケースもあります。ライセンス費用だけでなく、データ環境の整備や人材育成といった導入支援にかかるコストも考慮して、全体的な予算を計画することが重要です。
6-4. 他のBIツールと比べてPower BIの強みは何ですか?
A. Microsoft製品とのシームレスな連携(Excel, Teams, SharePointなど)、豊富なデータコネクタ、無料版から試しやすい点、コミュニティが活発で情報が得やすい点などが挙げられます。
6-5. Power BIを導入すれば、すぐにデータ活用が進みますか?
A. いいえ、ツール導入はデータ活用の一歩に過ぎません。目的の明確化、データ品質の向上、組織内のデータリテラシー向上、運用体制の構築など、継続的な取り組みが必要です。
まとめ
Power BIは、誰もが手軽にデータ可視化に取り組めるBIツールです。初めてBIツールを使う人でも、オンプレミスデータベースからデータを取り込み、直感的な操作でグラフ化できる点が大きな特徴です。一方で、ツールを最大限に活用し、有益なデータ分析を行うためには、単なる操作スキルだけではなく、「何を知りたいのか」「何を伝えたいのか」という目的を明確にし、それに沿ったデータを視覚化する必要があります。Power BIは、個人利用なら無償で利用でき、有償のProライセンスも試用版が用意されています。データ分析に興味がある方は、まずは実際に触れてみて、その可能性を探ってみることをおすすめします。
\ データ活用についてのご相談はメンバーズデータアドベンチャーまで /
\ 相談する前に資料を見たいという方はこちら /
▶こちらも要チェック
2025年8月27日(水)~28日(木)に開催された、株式会社アイスマイリー主催『AI博覧会 Summer 2025』にて白井が登壇したセッション「生成AI活用の展望と、ROIが出る業務実装のポイント」のアーカイブ動画が配信開始しました。
※視聴フォームの送信が必要です
登壇内容については以下をご確認ください。
株式会社アイスマイリー主催『AI博覧会 Summer 2025』にカンパニー社長の白井恵里が登壇します
2025年11月25日(火)に開催される、一般社団法人データサイエンティスト協会主催『12thシンポジウム インターセクション〜交わることで生まれる、新たなデータの価値〜』にて弊社の広報 小池 育弥がパネラーとして登壇します。
登壇概要
- データサイエンティスト協会 12thシンポジウム インターセクション〜交わることで生まれる、新たなデータの価値〜
- 日時:2025年11月25日(火)10:00〜18:25(受付:9:00〜) / 懇親会 18:30〜20:30
会場:ウェスティンホテル東京
主催:一般社団法人データサイエンティスト協会 - 登壇セッション:データサイエンス×教育セッション
- 詳細・参加申込:データサイエンティスト協会 12thシンポジウム インターセクション〜交わることで生まれる、新たなデータの価値〜
登壇者紹介
小池 育弥(こいけ いくみ)

株式会社メンバーズ
メンバーズデータアドベンチャーカンパニー
広報室 広報G
新卒で宿泊施設コンサルティング企業に入社し、営業、営業企画、採用育成、広報を経験。その後、新電力にてマーケティングに携わる。
データアドベンチャーカンパニーでは広報としてアウター・インナーブランディングを推進。
データ人材である社員や顧客へのインタビュー、コミュニケーションを通じて、社員エンゲージメントやブランド価値の向上などに取り組んでいる。
レバレジーズ株式会社の運営するエンジニア向けメディア『freelance hub(フリーランスハブ)』の「入門から実践まで!データサイエンス学習や情報収集に役立つメディア・ブログまとめ」に弊社が紹介されました。
「メディア」では、社員の専門知識や経験を活かし実践的なデータ活用ノウハウを発信しております。
詳細につきましてはお問い合わせください。
2025年11月7日(金)に開催される、東京農業大学総合研究所主催『第5回公開シンポジウム「食・農データサイエンス」』に弊社のデータサイエンティスト 武藤 賢悟が登壇します。
登壇概要
- 第5回公開シンポジウム「価値づくりからEC戦略まで、多様な事例で学ぶ 食・農データサイエンス」
日時:2025年11月7日(金)12:50~17:10
会場:東京農業大学 世田谷キャンパス 榎本ホール
主催:東京農業大学総合研究所研究会 食・農データサイエンス部会
共催:稲・コメ・ごはん部会 - 登壇セッション:ECマーケティングの戦略設計に対する時系列モデリングの適用
- 詳細・参加申込:【総研研究会】第5回公開シンポジウム「食・農データサイエンス」開催について
登壇者紹介
武藤 賢悟(むとう けんご)
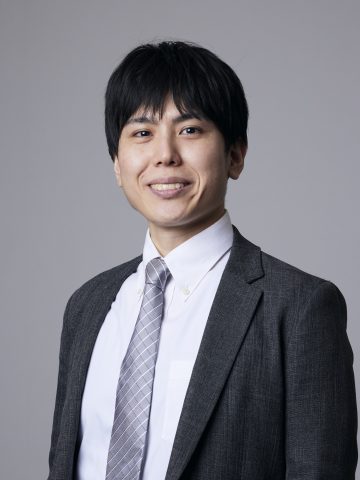
株式会社メンバーズ
メンバーズデータアドベンチャーカンパニー
サービス開発室 データサイエンスG
データサイエンティスト
東北大学薬学部大学院修了後、大手食品メーカーにて統計解析を含む研究業務および商品開発に従事。
その後2021年にDAへ中途入社し、現在までEC事業会社に常駐。ほか、教育事業会社や化粧品会社への常駐経験を経て、現在に至る。
データアドベンチャーカンパニーではサービス開発室に所属し、データサイエンティストとして高度な分析手法を用いることで、クライアントのビジネス成果創出に貢献している。
2025年9月30日に『PR TIMES STORY』にて弊社の生成AI活用促進に関する記事を配信しました。
メンバーの生成AI活用レベルを高めることで常駐業務を効率化・高度化。顧客への提供価値を高めるメンバーズデータアドベンチャーの取り組み。(PR TIMES STORY)
ぜひご覧ください。
「データ分析を専門の会社に依頼したいけれど、どの会社がおすすめなのかわからない」「自社のビジネス課題を本当に解決してくれるパートナーを見つけたい」
このような悩みを抱えていませんか?データ分析会社の選定は、ビジネスの成果を大きく左右する非常に重要な決断です。
本記事では、多数の企業のデータ活用を支援してきた専門家が、失敗しないデータ分析会社の選び方を5つの重要ポイントに絞って徹底解説します。さらに、2025年の最新情報に基づき、厳選したおすすめのデータ分析会社13社を比較し、貴社に最適な一社を見つけるお手伝いをします。
この記事を読めば、信頼できるパートナーを見極め、データ活用を成功に導くための具体的な方法が明確になります。
▶目次

開催日 2026.01.27 (火) 11:00~12:00
AI導入でROIを生み出したいマネージャー・リーダー層や社内推進担当者必見。他社事例やトレンドを交え、業務実装のポイントを解説します。
01.【超重要】データ分析会社選びで失敗しないための5つのポイント
データ分析を外注する際に、会社の知名度や料金だけで選んでしまうと、「期待した成果が得られなかった」「レポートはもらったが、次の一手に繋がらない」といった失敗に陥りがちです。ここでは、データ分析会社の選定で絶対に外せない5つの超重要なポイントを解説します。
- ・課題解決の実績・専門性 :自社の業界・課題に合っているか
- ・分析力と技術力 :課題解決に必要な分析手法を扱えるか
- ・伴走力と支援体制 :戦略から実行、内製化まで支援してくれるか
- ・コミュニケーション力 :専門用語を避け、分かりやすく説明してくれるか
- ・セキュリティ体制 :信頼できる情報管理体制が整っているか
これらの視点を持つことで、真にビジネスの成長に貢献してくれるパートナーを見極めることができるようになります。
1-1.課題解決の実績・専門性:自社の業界・課題に合っているか
データ分析会社を選ぶ上で最も重要なのは、自社の業界や課題に特化した実績と専門性を持っているかを確認することです。 業界特有の商習慣や顧客行動への理解がなければ、分析結果が表層的になり、真の課題解決には繋がりません。
例えば、製造業であれば生産管理や需要予測、小売業であれば顧客の購買行動やWebサイトのログ解析といった、それぞれの業界に特有のデータ分析ノウハウが存在します。会社のWebサイトで公開されている導入事例を確認し、自社と同じ業界、あるいは類似した課題を解決した実績が豊富にあるかを見極めることが重要です。
自社のビジネスに直結する課題解決の実績がある会社を選ぶことが、成功への最短ルートとなります。
1-2.分析力と技術力:課題解決に必要な分析手法を扱えるか
課題を解決するためには、会社が適切な分析手法とそれを支える高い技術力を保有しているかを見極めることが不可欠です。 データ分析と一口に言っても、現状を可視化するレポート作成から、統計解析による需要予測、さらにはAI(人工知能)を用いた高度な機械学習モデルの構築まで、目的によって求められる技術レベルは大きく異なります。
1-3.伴走力と支援体制:戦略から実行、内製化まで支援してくれるか
分析レポートを提出して終わりではなく、戦略策定から施策の実行、さらには将来的なデータ活用の内製化まで一貫して支援してくれる「伴走力」が極めて重要です。 データ分析は、結果をビジネスアクションに繋げて初めて価値が生まれます。
そのためには、企業の現場に寄り添い、長期的な視点で課題解決をサポートしてくれるパートナーの存在が欠かせません。優れたパートナーは、分析結果から具体的な改善施策を提案し、その実行までをサポートします。
さらに、データ分析組織の立ち上げ支援や人材育成プログラムを提供し、最終的に企業が自走できる体制の構築までを見据えています。中長期的なパートナーとして企業のデータドリブン文化醸成までを視野に入れた支援体制が整っているかを確認しましょう。
1-4.コミュニケーション力:専門用語を避け、分かりやすく説明してくれるか
データ分析の専門家でない担当者にも理解できるよう、専門用語を避け、平易な言葉で分かりやすく説明してくれる高いコミュニケーション能力を持つ会社を選ぶべきです。 分析結果がどれだけ高度で正確でも、その内容がビジネスサイドの意思決定者に伝わらなければ、具体的なアクションには繋がりません。
分析担当者と事業担当者の間に認識の齟齬が生まれると、プロジェクトが頓挫する原因にもなりかねません。契約前の打ち合わせの段階で、こちらの話を丁寧に傾聴し、図や具体例を用いて視覚的に説明してくれるかどうかが、信頼できるパートナーを見極める一つの判断基準となります。
担当者の説明が明快で、こちらの意図を正確に汲み取ってくれるかどうかを、実際の対話の中でしっかりと見極めることが大切です。
1-5.セキュリティ体制:信頼できる情報管理体制が整っているか
企業の機密情報や顧客の個人情報など、重要なデータを預ける以上、堅牢なセキュリティ体制が整備されていることは絶対条件です。 万が一、情報漏洩などのセキュリティインシデントが発生すれば、顧客からの信頼を失い、法的な責任を問われるなど、企業に計り知れない損害をもたらします。
02.【2025年最新】データ分析でおすすめの会社13選を徹底比較
データ分析会社の選定は、ビジネスの成果を大きく左右する重要な決断です。しかし、各社の強みや専門領域は多岐にわたるため、どの会社が自社に最適かを見極めるのは簡単ではありません。
そこで、ここでは2025年の最新情報に基づき、実績や専門性、支援体制などの観点から厳選した13社を徹底的に比較・解説します。各社の特徴を理解し、自社の課題解決に最も貢献してくれるパートナーを見つけましょう。
| 会社名 | 得意領域 | 特徴 | こんな会社におすすめ |
|---|---|---|---|
| メンバーズ データアドベンチャーカンパニー | 戦略策定、データ活用・分析実行支援、内製化 | 専門家が常駐し、伴走型で支援 | 戦略から実行まで一気通貫で支援してほしい |
| ブレインパッド | 業界横断的なデータ活用支援 | 1,300社以上の豊富な支援実績 | 幅広い業界で実績のある会社に依頼したい |
| ARISE analytics | AI・機械学習、通信データ活用 | KDDIとアクセンチュアの知見を融合 | 高度な分析技術や通信データを活用したい |
| マクロミル | マーケティングリサーチ | 国内最大級の消費者パネルデータを保有 | 消費者インサイトに基づいた分析をしたい |
| データフォーシーズ | 統計解析、医療・ヘルスケア | 統計モデル構築と医療データ分析に定評 | 統計的根拠の強い専門的な分析をしたい |
| インテージテクノスフィア | リサーチテクノロジー、システム開発 | 国内最大手リサーチ会社の技術基盤 | 大規模な調査データの収集・分析基盤が必要 |
| AVILEN | AI人材育成、AI開発 | AI人材育成から開発まで一気通貫で支援 | AI開発と同時に社内のAIスキルを向上させたい |
| pluszero | 自然言語処理、数理最適化 | 独自開発のAIエンジンに強み | 自然言語処理や数理最適化の課題がある |
| データビークル | データサイエンスツール提供 | 専門家でなくても使える分析ツールが特徴 | ツールを活用して分析業務を効率化したい |
| unerry | OMO支援、リアル行動データ | GPS等を用いたリアルな人流データを活用 | 店舗への集客などオフライン施策を強化したい |
| True Data | 購買データ分析 | 全国のスーパーやドラッグストアの購買データ | 小売向けのデータに基づいた商品開発や販促がしたい |
| サイカ | 広告効果測定 | 統計分析で広告の貢献度を可視化 | テレビCMなどオフライン広告の効果を測定したい |
| アクセンチュア | 総合コンサルティング、DX推進 | 戦略から実行までグローバルな知見を提供 | 全社的なDX推進や大規模プロジェクトを相談したい |
2-1.株式会社メンバーズ データアドベンチャーカンパニー|データ活用を戦略から実行まで伴走する共創パートナー

画像出典「 株式会社メンバーズ データアドベンチャーカンパニー 」
株式会社メンバーズの社内カンパニーであるデータアドベンチャーは、データ活用戦略の策定から施策の実行、さらには組織への内製化支援までを一気通貫で伴走するデータ活用コンサルティング・内製化支援パートナーです。 データサイエンティストやアナリスト、エンジニアといった専門家が顧客のチームに常駐する形で参画し、ビジネス課題の解決に直接コミットします。
この手法により、単に分析レポートを納品するだけでなく、現場の状況を深く理解し、ビジネス成果に直結する実用的な施策を共に推進することが可能です。データ活用を始めたいが何から手をつければ良いかわからない企業や、分析を次のアクションに繋げられずに悩んでいる企業にとって、心強い味方となるでしょう。
2-2.株式会社ブレインパッド|業界トップクラスの実績を誇るリーディングカンパニー

画像出典「株式会社ブレインパッド」
株式会社ブレインパッドは、2004年の創業以来、データ活用の支援に特化してきた業界のパイオニアです。 特筆すべきは、業界を問わず1,300社を超える圧倒的な支援実績に裏打ちされた、課題解決能力の高さです。
長年の経験で培われた分析ノウハウと、最新のAI技術を組み合わせ、企業の経営課題に的確なソリューションを提供します。金融、製造、通信、小売など、あらゆる業界のトップ企業を支援してきた実績は、その実力の証左と言えるでしょう。
データ分析の専門企業として初めて東証一部に上場した信頼性もあり、大規模で複雑な課題を抱える企業や、業界のベストプラクティスを参考にしたい企業におすすめです。
2-3.株式会社ARISE analytics|KDDIとアクセンチュアの知見を融合した高度な分析力

画像出典「株式会社ARISE analytics」
株式会社ARISE analyticsは、KDDIが保有する国内最大規模のデータと、世界的なコンサルティングファームであるアクセンチュアの高度な分析ノウハウを融合させて誕生したデータサイエンティスト集団です。 通信キャリアならではの膨大な顧客接点データと、最先端のAI技術を掛け合わせることで、高精度な未来予測や顧客インサイトの抽出を得意としています。
例えば、通信サービスの解約予測モデルや、顧客一人ひとりに最適なサービスを提案するマーケティング支援などで豊富な実績があります。通信データというユニークなアセットを活用したい企業や、AIを用いた高度な分析で競合との差別化を図りたい企業にとって、唯一無二の価値を提供してくれる会社です。
2-4.株式会社マクロミル|豊富なリサーチデータと分析力を融合

画像出典「株式会社マクロミル」
株式会社マクロミルは、マーケティングリサーチ業界のリーディングカンパニーであり、その強みは国内最大級の消費者パネルから得られる膨大なリサーチデータにあります。 アンケート調査で収集した意識データと、実際の購買履歴などの行動データを組み合わせることで、生活者のインサイトを多角的に深く掘り下げることができます。
新商品のコンセプト評価や広告効果測定、顧客満足度調査など、マーケティングに関わるあらゆる課題に対して、データに基づいた的確な意思決定を支援します。自社だけでは得られない客観的な市場データや、生活者のリアルな声を取り入れたデータ分析を行いたい企業にとって、最適なパートナーです。
2-5.データフォーシーズ株式会社|統計解析・数理モデルの構築に定評

画像出典「データフォーシーズ株式会社」
データフォーシーズ株式会社は、創業以来、科学的なアプローチに基づくデータ解析サービスを提供している専門家集団です。 特に、統計解析や数理最適化といった高度な分析手法を用いた予測モデルの構築に定評があり、医療・ヘルスケア分野で豊富な実績を誇ります。
例えば、レセプトデータ(診療報酬明細書)や健診データを解析し、疾病リスクを予測するモデルを開発するなど、社会貢献性の高いプロジェクトを数多く手掛けています。製薬会社や研究機関を主要取引先としており、その高い技術力と専門性がうかがえます。
統計的な信頼性の高い分析や、専門領域における高度な予測モデル開発を求める企業に適しています。
2-6.株式会社インテージテクノスフィア|マーケティングリサーチ国内最大手の技術基盤

画像出典「株式会社インテージテクノスフィア」
株式会社インテージテクノスフィアは、アジアNo.1のマーケティングリサーチ企業であるインテージグループのIT・技術開発を担う中核企業です。 国内最大級のパネル調査を支える大規模なデータ収集・処理基盤の構築・運用ノウハウが最大の強みです。
SNSの普及やマルチデバイス化によって複雑化する現代の生活者の行動を360度理解するため、最新のテクノロジーを駆使して膨大なデータを迅速かつ正確に処理するシステムを開発しています。マーケティングリサーチにおけるデータ収集から集計、分析システムの開発まで、全ての工程をワンストップで実現できる技術力があります。
信頼性の高い大規模な調査システムやデータ基盤を構築したい企業にとって、これ以上ないパートナーと言えるでしょう。
2-7.株式会社AVILEN|AI人材育成から開発まで一気通貫で支援

画像出典「株式会社AVILEN」
株式会社AVILENは、AIソリューション開発とAI人材育成の2つの事業を柱とする企業です。 AIモデルの開発・導入支援に留まらず、クライアント企業内でAIを使いこなせる人材を育てるための研修プログラムまでを一気通貫で提供している点が最大の特徴です。
E資格(JDLA Deep Learning for ENGINEER)の合格者数トップクラスの実績が示すように、質の高い教育コンテンツに定評があります。この「開発」と「育成」の両輪を回すことで、外部パートナーに依存するだけでなく、将来的には企業が自走してDXを推進できる体制の構築を支援します。
AIプロジェクトを成功させたいと同時に、社内のAIリテラシー向上やデータ活用文化の醸成を目指す企業に強くおすすめします。
2-8.株式会社pluszero|自然言語処理や数理最適化に特化
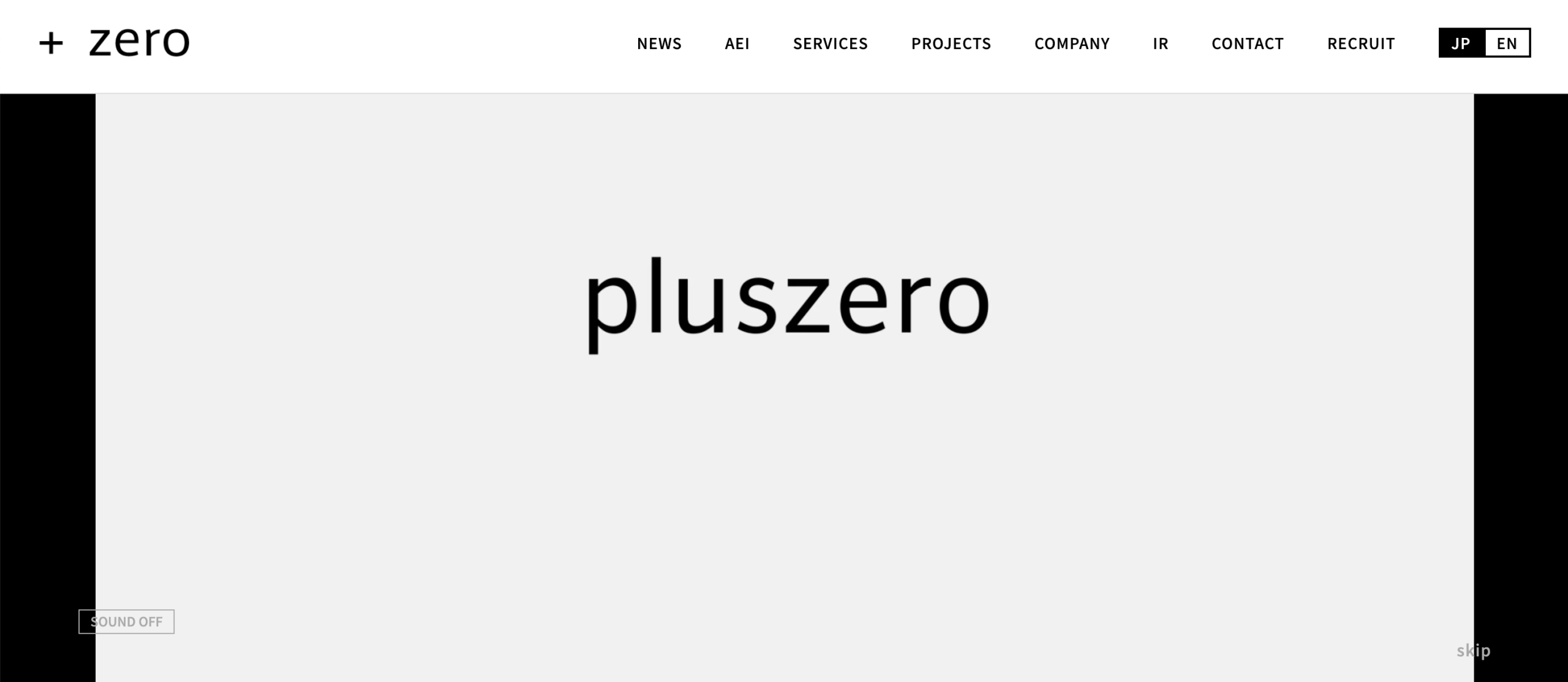
画像出典「株式会社pluszero」
株式会社pluszero(プラスゼロ)は、AIの中でも特に自然言語処理(NLP)や数理最適化といった領域に強みを持つ技術開発企業です。 人の言葉や意図を理解する独自開発のAIエンジン「AEI」を基盤に、企業の様々な課題を解決するソリューションを提供しています。
例えば、膨大な問い合わせログやアンケートの自由記述テキストを解析して業務改善のヒントを発見したり、複雑な条件の中から最適な組み合わせを見つけ出す生産計画の最適化などが得意分野です。人間の思考や感覚に近い判断が求められる高度な課題に対して、オーダーメイドのAIソリューションで応える技術力があります。
テキストデータの活用や、複雑なオペレーションの効率化といった課題を持つ企業にとって、非常に魅力的な選択肢です。
2-9.株式会社データビークル|専門知識不要のデータサイエンスツールを提供

画像出典「株式会社データビークル」
株式会社データビークルは、「データサイエンスを全ての人に」というビジョンのもと、専門家でなくても使いこなせるデータ分析ツールを提供している会社です。 主力製品である「data-beagle」は、統計学やプログラミングの知識がなくても、マウス操作だけで高度なデータ分析や需要予測を行えるよう設計されています。
分析のプロセスが自動化されており、ユーザーはビジネス課題の探求に集中することができます。ツールの提供だけでなく、データ分析の専門家による導入・活用支援も充実しており、分析文化の組織への定着をサポートします。
データ分析の内製化を進めたいが、専門人材の採用や育成に課題を抱えている企業にとって、強力なソリューションとなるでしょう。
2-10.株式会社unerry|リアル行動データプラットフォームでOMOを支援
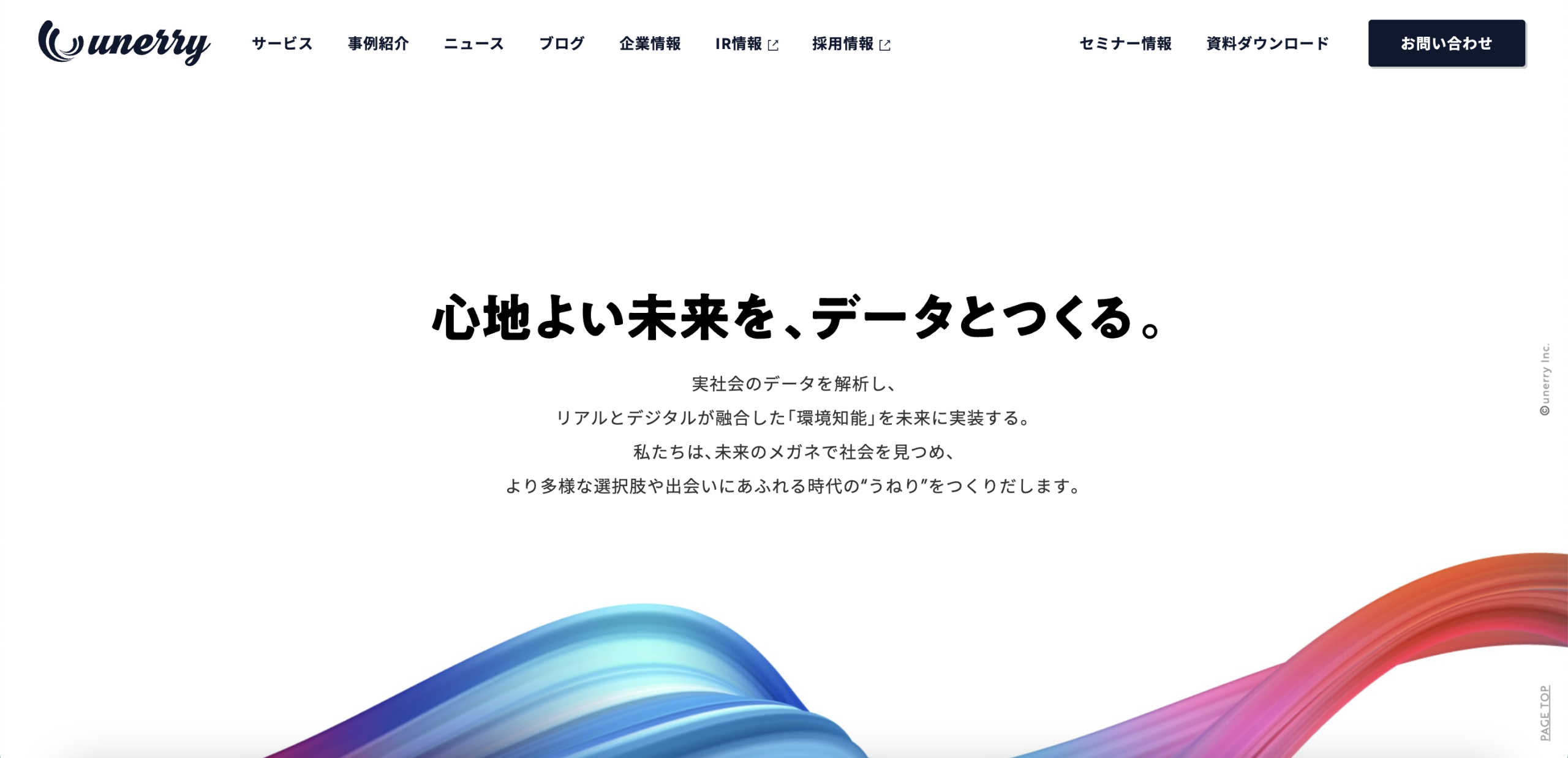
画像出典「株式会社unerry」
株式会社unerry(ウネリー)は、スマートフォンのGPSやビーコンなどから得られるリアルな人々の行動データを活用したマーケティング支援を得意とする会社です。 同社が提供する「Beacon Bank」は、国内最大級のリアル行動データプラットフォームであり、顧客が「いつ、どこにいたか」という情報を高精度に捉えることができます。
このデータを活用することで、特定エリアへの来訪者にターゲティング広告を配信したり、店舗への来店効果を可視化するなど、オンラインとオフラインを融合させたOMO(Online Merges with Offline)戦略を強力に推進します。実店舗への送客を増やしたい小売業や、イベントの効果を測定したい事業者など、オフラインでの成果を重視する企業におすすめです。
2-11.株式会社True Data|全国の購買データを活用したマーケティング分析
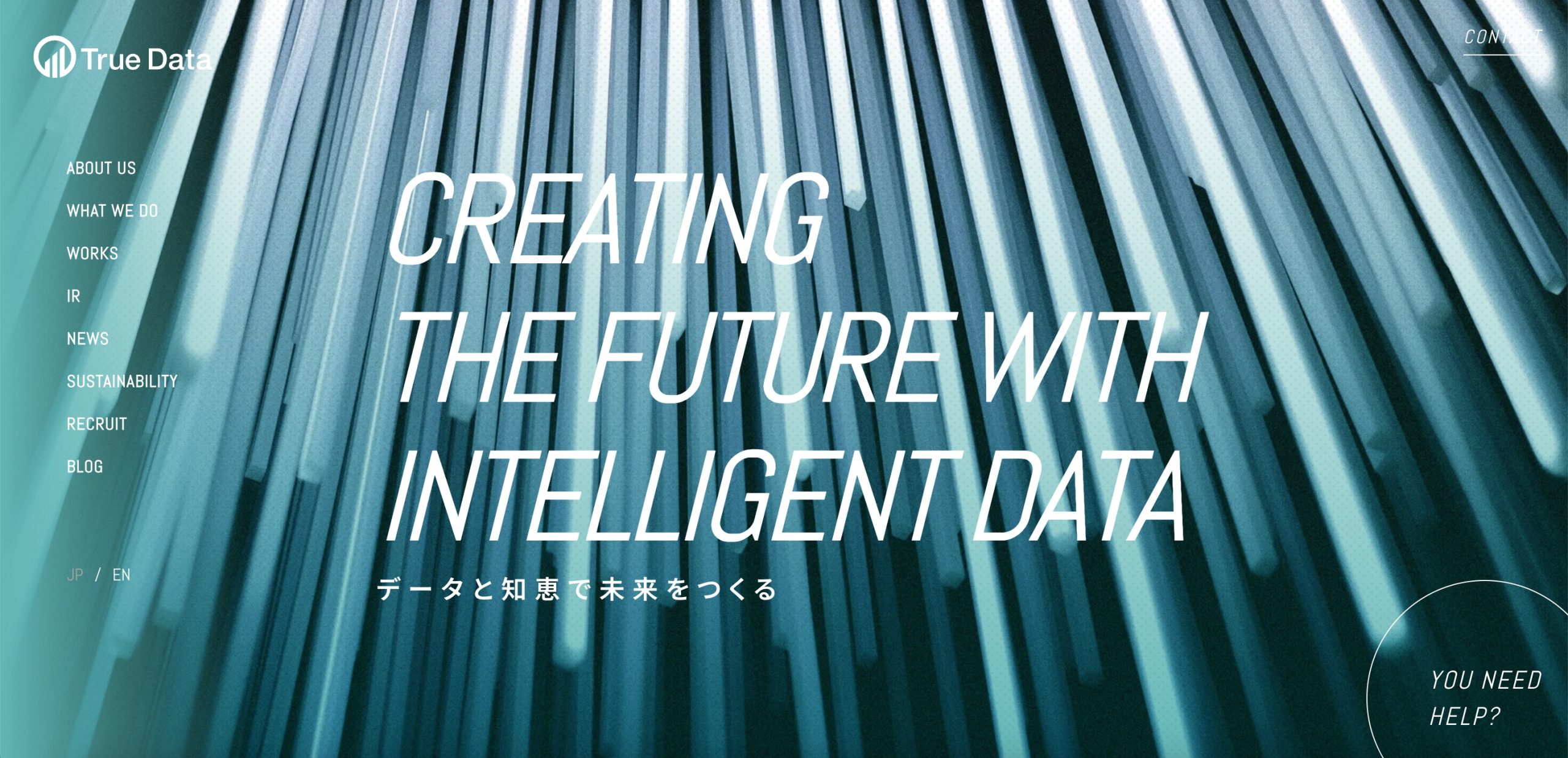
画像出典「株式会社True Data」
株式会社True Data(トゥルーデータ)は、全国のスーパーマーケットやドラッグストアなどから収集した年間1,000億規模の膨大な購買データ(ID-POSデータ)を保有・分析している会社です。 この実購買データを用いることで、「誰が」「いつ」「どこで」「何を」「いくつ」「いくらで」買ったかという消費者の購買行動を事実ベースで正確に捉えることができます。
メーカーの新商品開発における需要予測や、小売店の棚割り最適化、販促キャンペーンの効果測定など、データに基づいた精度の高いマーケティング施策の立案を支援します。消費者インサイトを事実データに基づいて深く理解し、商品開発やマーケティング戦略に活かしたい消費財メーカーや小売業にとって、欠かせないパートナーです。
2-12.株式会社サイカ|統計分析で広告効果を可視化する「XICA magellan」
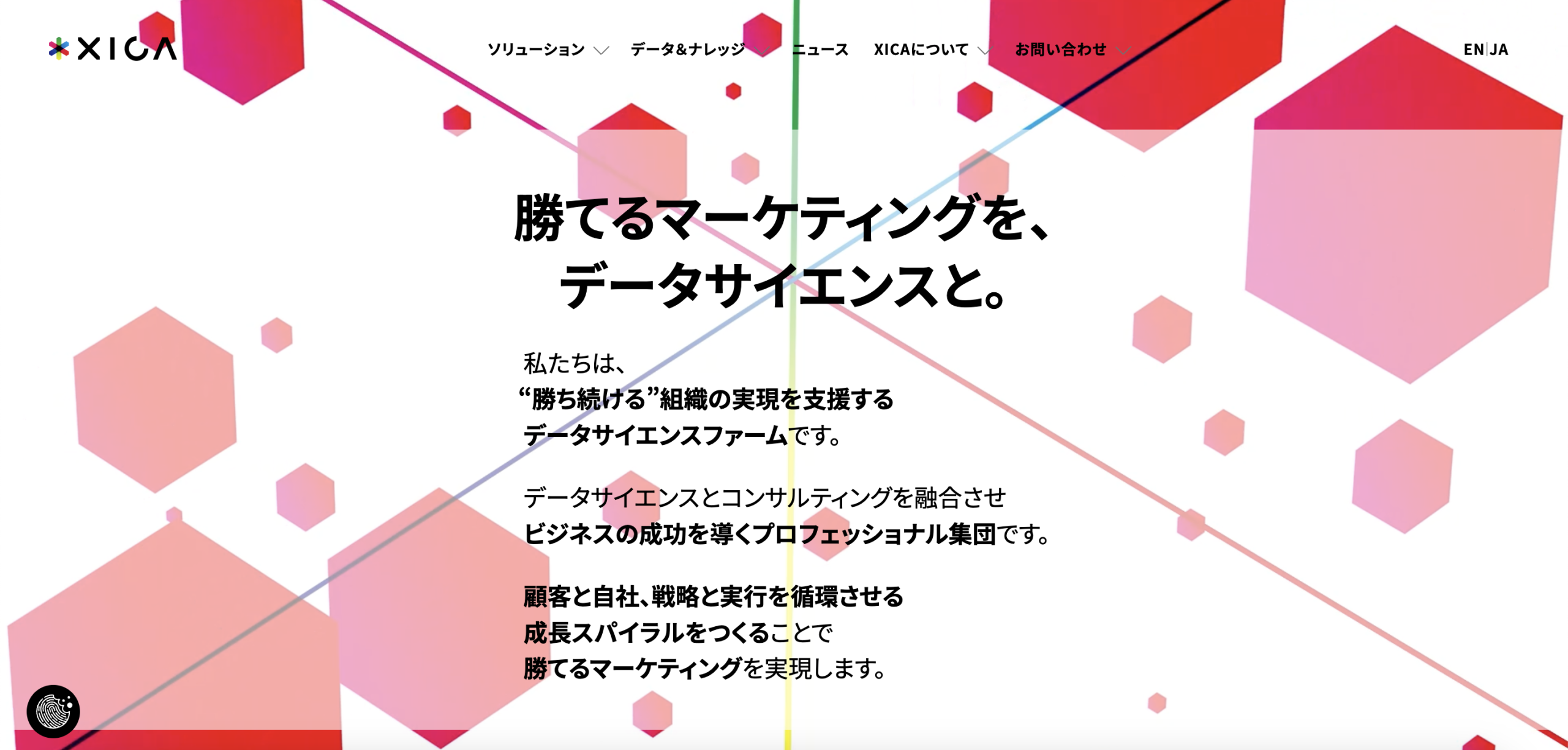
画像出典「株式会社サイカ」
株式会社サイカは、統計分析を強みとし、特に広告効果測定の分野で高い評価を得ている会社です。 主力製品である「XICA magellan(サイカ マゼラン)」は、テレビCMや交通広告といったオフライン広告の効果を統計的に分析し、売上への貢献度を可視化することができるツールです。
従来は効果測定が難しいとされてきたオフライン広告と、Web広告の効果を統合的に分析することで、広告予算の最適な配分(メディアミックス)を支援します。多額の広告費を投下している企業にとって、データに基づいた客観的な根拠を持ってマーケティング投資の意思決定を行えるようになります。
広告宣伝費のROI(投資対効果)を最大化したいと考えるすべての企業におすすめです。
2-13.アクセンチュア株式会社|総合コンサルティングファームの豊富な知見

画像出典「アクセンチュア株式会社」
アクセンチュア株式会社は、世界最大級の総合コンサルティングファームであり、データとアナリティクスは同社が提供するサービスの中核をなしています。 最大の強みは、特定の分析手法やツールに留まらず、企業の経営戦略レベルからデジタルトランスフォーメーション(DX)全体の構想を描き、その実行までをエンドツーエンドで支援できる総合力にあります。
各業界に精通したコンサルタントと、データサイエンティスト、エンジニアが連携し、企業の最も困難な課題に対して、グローバルで培われた豊富な知見と方法論を駆使して解決策を導き出します。全社的なデータ活用戦略の策定や、大規模な基幹システムの刷新など、経営レベルの大きな変革を目指す企業にとって、最も信頼できるパートナーの一つです。
03.【目的・課題別】あなたの会社に合うデータ分析会社はどこ?3つの分類で解説
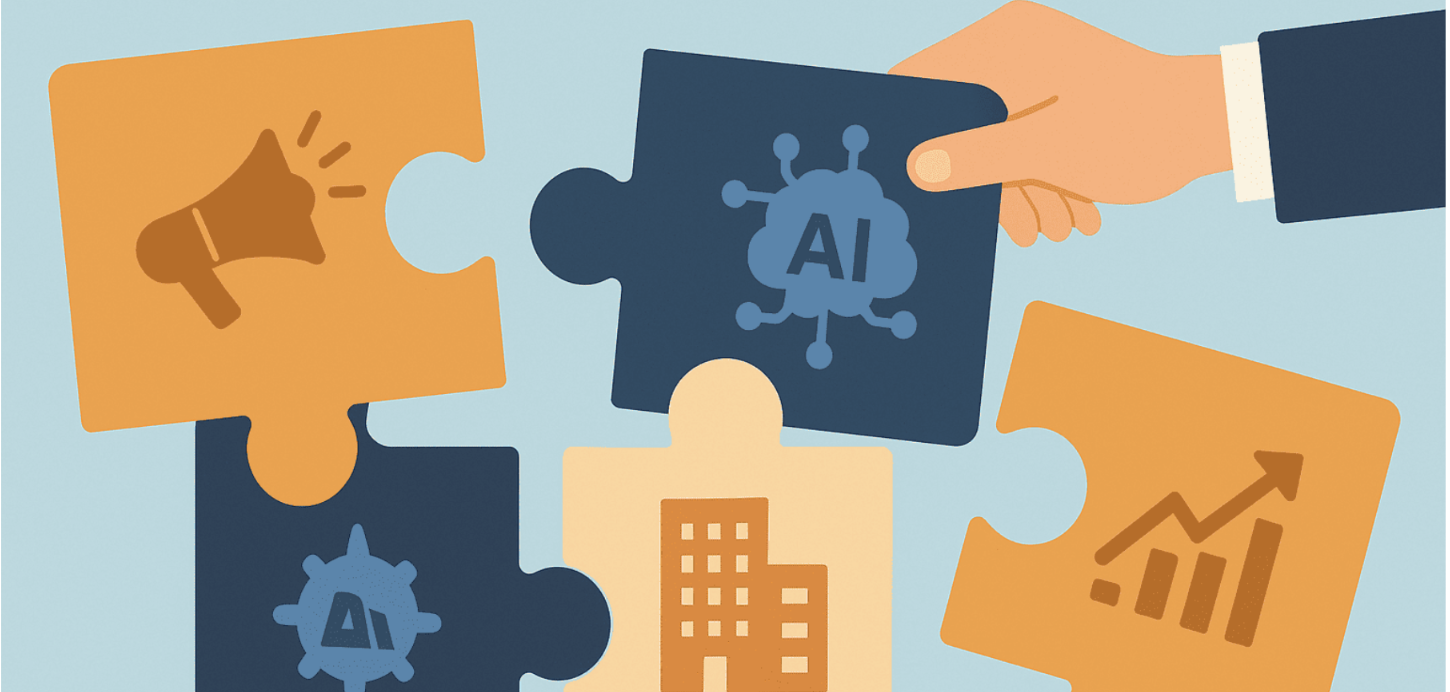
データ分析会社を選ぶ際は、自社の目的や課題を明確にし、それに合致した強みを持つパートナーを見つけることが成功の鍵です。ここでは、代表的な3つの目的に分類し、それぞれの課題解決に最適な会社を具体的に解説します。
- マーケティング成果を最大化したい
- 高度なAIモデルを構築したい
- DX推進と内製化を実現したい
あなたの会社のニーズに最もマッチする一社を見極めましょう。
3-1.マーケティング成果を最大化したいならこの3社
顧客の行動や市場のトレンドを正確に把握し、データに基づいたマーケティング施策を実行することは、ビジネス成長に不可欠です。ここでは、顧客データの分析から広告効果の最適化まで、マーケティング成果の向上に直結する強みを持つ3社を紹介します。
株式会社メンバーズ データアドベンチャーカンパニー
データ分析から施策の実行、改善までを一気通貫で支援し、マーケティングのPDCAサイクルを高速で回したい企業に最適です。同社は、専門家が顧客のチームに常駐して伴走するスタイルを特徴としており、分析結果を具体的なアクションに繋げる実行力に長けています。
株式会社ブレインパッド
業界を問わず1,300社以上の豊富な支援実績があり、多様なマーケティング課題に対応できるノウハウを求める企業におすすめです。顧客データの分析基盤構築から需要予測、デジタルマーケティング支援まで、幅広いサービスを提供しています。
株式会社サイカ
テレビCMなどオフライン広告を含めた、広告宣伝費全体の投資対効果(ROI)を最大化したい企業にとって最高のパートナーです。主力製品「XICA magellan」は、従来は効果測定が困難だった広告がどれだけ売上に貢献したかを科学的に可視化します。
3-2.高度なAI・機械学習モデルを構築したいならこの2社
AIや機械学習の技術は、需要予測の高度化、製品の異常検知、顧客へのレコメンドなど、ビジネスに大きな変革をもたらす可能性を秘めています。ここでは、オーダーメイドのAIモデル開発や、特定の技術領域で高い専門性を持つ2社を紹介します。
株式会社ARISE analytics
国内最大規模のデータを活用した高精度なAIモデルや、最先端の分析ノウハウを求める企業におすすめです。KDDIが持つ膨大な顧客データと、アクセンチュアのグローバルな分析知見を融合させた、国内有数のデータサイエンティスト集団です。
株式会社pluszero
自然言語処理(人の言葉を扱う技術)や数理最適化など、特定の専門領域で高度なAI開発を必要とする企業にとって頼れる存在です。独自に開発したAIエンジンを基盤に、人間の思考や意図を理解するAIソリューションを提供しています。
3-3.DXを全社的に推進し、データ活用を内製化したいならこの2社
デジタルトランスフォーメーション(DX)を成功させるためには、外部パートナーに頼るだけでなく、最終的に社内にデータ活用の文化を根付かせ、自走できる体制(内製化)を構築することが不可欠です。ここでは、戦略立案から組織作り、人材育成までを視野に入れた支援を行う2社を紹介します。
株式会社メンバーズ データアドベンチャーカンパニー
専門家チームが顧客企業に常駐し、現場に伴走しながらデータ活用の文化醸成と内製化を推進したい企業に最適なパートナーです。単にシステムを導入するだけでなく、日々の業務の中でデータに基づいた意思決定プロセスを共に構築し、実践を通じて社員のスキルアップを支援します。
アクセンチュア株式会社
経営戦略レベルから全社的なDXを構想し、グローバルな知見を活かした大規模な変革を目指す企業におすすめです。世界最大級の総合コンサルティングファームとして、戦略策定からシステム導入、組織変革、実行支援までをエンドツーエンドで提供できる総合力が強みです。
04.データ分析を外注する3つのメリット
データ分析の専門人材の確保が難しい、あるいは分析にまで手が回らないという企業にとって、外注は非常に有効な選択肢です。専門家の力を借りることで、自社だけで最適なパートナーを見つけるのは簡単ではありません。ここでは、データ分析を外注することで得られる以下3つの主要なメリットを解説します。
- 最新の専門知識と技術を活用できる
- 客観的な視点から新たなインサイトを得られる
- コア業務に集中し、迅速な意思決定が可能になる
4-1.最新の専門知識と技術を活用できる
データ分析を外注する最大のメリットは、社内に専門家がいなくても、データサイエンスの高度な専門知識と最新技術をすぐに活用できる点です。 データ分析の世界は、AIや機械学習などの技術が日々進化しており、そのすべてを自社でキャッチアップし続けるのは容易ではありません。
データ分析会社には、多様な分析手法に精通した専門家が在籍しており、常に最新の知識とツールを駆使して課題解決にあたります。これにより、自社で高額な人件費をかけて専門家を雇用・育成することなく、必要な時に最高の分析能力を活用することが可能になります。
4-2.客観的な視点から新たなインサイトを得られる
社内の人間では気づきにくい「当たり前」や「思い込み」から解放され、第三者の客観的な視点によって新たなビジネスチャンスや課題を発見できることも大きなメリットです。 長く同じ事業に携わっていると、どうしても視野が狭くなったり、既存の成功体験に縛られたりしがちです。
外部の専門家は、そうした社内の常識にとらわれることなく、データそのものをフラットな目で分析します。その結果、これまで見過ごされていた顧客セグメントや、意外な相関関係といった、事業成長に繋がる貴重なインサイト(洞察)が得られることがあります。
4-3.コア業務に集中し、迅速な意思決定が可能になる
データ収集や分析といった専門的で時間のかかる作業を専門家に任せることで、自社の従業員は本来注力すべきコア業務にリソースを集中させることができます。 データ分析は、データの準備から分析、レポーティングまで多くの工数を要します。
このプロセスを外注することで、例えばマーケティング担当者は施策の企画・実行に、営業担当者は顧客との関係構築に、より多くの時間を割けるようになります。また、専門家による迅速な分析結果は、ビジネス環境の変化に対応したスピーディな意思決定を可能にし、競争優位性の確保に繋がります。
05.データ分析の外注で失敗しないための3つの注意点
データ分析の外注は多くのメリットがある一方で、ポイントを抑えずに進めると「期待した成果が出なかった」という結果に終わりかねません。外注を成功に導き、投資対効果を最大化するために、依頼前に必ず確認すべき以下3つの注意点を解説します。
- 目的と課題を丸投げにせず、明確に共有する
- 必要なデータが整備されているか事前に確認する
- 委託範囲と責任の所在を明確にする
5-1.目的と課題を丸投げにせず、明確に共有する
「とりあえずデータを分析してほしい」といった丸投げの依頼は、失敗の典型的なパターンです。 データ分析によって「何を明らかにしたいのか」「どんな課題を解決したいのか」という目的を、可能な限り具体的に共有することが最も重要です。
外注先のパートナーは、あなたの会社のビジネス背景を完全には理解していません。例えば「売上を伸ばしたい」という漠然とした要望ではなく、「どの顧客セグメントにアプローチすればLTV(顧客生涯価値)が最大化するか知りたい」というように具体化することで、分析の精度は格段に上がります。
目的が明確であればあるほど、得られるアウトプットも価値あるものになります。
5-2.必要なデータが整備されているか事前に確認する
分析の質はデータの質に大きく左右されるため、分析に必要なデータがそもそも存在するのか、利用可能な状態で整備されているのかを事前に確認する必要があります。 どれほど優秀な分析会社でも、元となるデータが不十分であったり、項目がバラバラであったり(いわゆる「汚いデータ」)すれば、正確な分析は行えません。
場合によっては、分析作業の前に、データを整理・統合する「データクレンジング」の工程に多大な時間とコストがかかることもあります。外注先に相談する前に、自社でどのようなデータが、どのような形式で、どの程度の期間蓄積されているのかを棚卸ししておくことが重要です。
5-3.委託範囲と責任の所在を明確にする
「どこからどこまでを依頼するのか」という委託範囲、成果物の定義、納期、そして双方の責任の所在を、契約前に書面で明確に合意しておくことがトラブル回避の鍵です。 例えば、「レポートの提出」がゴールなのか、「施策の提案」まで含むのか、あるいは「施策の実行支援」までを依頼するのかによって、費用や体制は大きく変わります。
また、個人情報などの機密データを扱う場合は、セキュリティポリシーの遵守や管理体制についても厳格に取り決めておく必要があります。曖昧な点をなくし、お互いの期待値をすり合わせることが、プロジェクトを円滑に進める上で不可欠です。
06.気になる費用は?データ分析の外注にかかる料金相場と体系

データ分析を外注する際に、最も気になるのが費用です。料金は、依頼する内容の難易度や期間、必要な専門家のスキルレベルによって大きく変動します。
ここでは、一般的な料金体系と、依頼内容別の費用相場について解説します。
6-1.料金体系は主に3種類(プロジェクト型・月額型・成果報酬型)
データ分析の料金体系は、主に以下の3つに分類されます。
・プロジェクト型
特定の分析課題に対して、成果物と納期を定めて一括で見積もる形式です。単発の依頼に適しています。
・月額型(リテイナー契約)
コンサルティングや継続的なレポーティングなど、中長期的な伴走支援を依頼する場合に用いられ、毎月定額の費用が発生します。
・成果報酬型
分析によって得られた売上向上分の一部を報酬として支払う形式です。ただし、分析の貢献度を正確に測ることが難しいため、採用されるケースは限定的です。
6-2.【料金表】依頼内容別の費用相場
依頼内容ごとの大まかな費用相場は以下の通りです。ただし、これらはあくまで目安であり、データの規模や複雑さ、求めるアウトプットのレベルによって変動します。
| 依頼内容 | 主な作業 | 料金相場(下限) |
|---|---|---|
| データ可視化・レポート作成 | BIツールでのダッシュボード構築、定型レポート作成 | 50万円~ |
| 統計解析・需要予測 | 統計モデルを用いた要因分析、将来予測 | 100万円~ |
| AI・機械学習モデル構築 | レコメンドエンジン、画像認識などの独自AI開発 | 300万円~ |
| データ活用コンサルティング・内製化支援 | 戦略立案、人材育成、組織構築の継続支援、ダッシュボード構築・運用、分析基盤構築・分析実行・運用 | 月額50万円~ |
・データ可視化・レポート作成:50万円~
散在するデータをBIツールなどで統合し、現状を把握するためのダッシュボードや定型レポートを作成する作業は、比較的安価な価格帯から依頼可能です。売上実績やWebサイトのアクセス状況などを可視化するシンプルなものを単発で作成するのであれば50万円程度から、複数のデータソースを扱う複雑なダッシュボード構築では100万円以上になることもあります。複数のダッシュボードの構築や運用が発生する場合は、それに応じて費用が高くなります。このような場合は、内製化支援の枠内で、月額型で発注するのもおすすめです。
・統計解析・需要予測:100万円~
過去のデータから将来の売上を予測したり、アンケート結果から顧客満足度に影響を与える要因を特定したりするなど、統計的な専門知識を要する分析は100万円程度からが相場となります。どのような分析手法を用いるか、どれだけ精緻なモデルを構築するかによって費用は大きく変動します。
・AI・機械学習モデル構築:300万円~
顧客一人ひとりに合わせた商品を推薦するレコメンドエンジンや、製造ラインでの異常検知システムなど、独自のAI・機械学習モデルをオーダーメイドで開発する場合は、最も高額な価格帯となります。最低でも300万円から、複雑なものでは数千万円規模になることも珍しくありません。
・データ活用コンサルティング・内製化支援:月額50万円~
特定の分析作業だけでなく、データ活用の戦略立案や組織体制の構築、人材育成など、中長期的に伴走してもらうコンサルティングは月額での契約が一般的です。専門家が週1回の定例会に参加してアドバイスを行うといった関わり方から、チームメンバーとして常駐してプロジェクトを推進する形まで、支援の深度によって月額50万円~数百万円と幅があります。チームメンバーとして常駐する形であれば、データ可視化・レポート作成、統計解析・需要予測、AI・機械学習モデル構築などデータに関わる業務を幅広く依頼できることがあります。
07.データ分析会社への依頼からプロジェクト開始までの3ステップ
データ分析会社への依頼は、思いつきで進めると期待した成果を得られない可能性があります。目的を明確にし、適切なパートナーを体系的に選定していくことが成功の鍵です。
ここでは、問い合わせからプロジェクト開始までを、3つの具体的なステップに分けて解説します。
- 問い合わせ・相談
- 提案・すり合わせ
- 契約・プロジェクト開始
7-1.問い合わせ・相談:課題の言語化
プロジェクトの最初のステップは、自社の課題感を整理し、パートナー候補となる企業に問い合わせて初期的な相談を行うことです。 この段階では、漠然とした「業務を効率化したい」「データを活用したい」といった課題を、専門家との対話を通じて具体的に言語化していくことが重要です。
企業のWebサイトや実績を確認し、自社の課題と親和性の高い企業を選定します。その上で、担当者との面談を通じて、自社のビジネス課題やデータ分析で実現したいことを明確に伝えます。この対話の中で、相手企業の担当者が自社のビジネスを深く理解し、的確な質問を投げかけてくれるかどうかを見極めることが、良いパートナーシップを築くための第一歩となります。
7-2.提案・すり合わせ:ゴールへの道筋を明確に
課題と目的が明確になったら、パートナー企業は具体的な解決策を盛り込んだ提案を作成してくれることが多いです。この提案は、プロジェクトのゴールとその達成に向けた道筋を示すものです。
提案書には、プロジェクトの背景、解決すべき課題、具体的な分析手法、期待される効果、そしてプロジェクトの進め方などが記載されます。この内容について、双方が納得できるまで議論を重ね、すり合わせ を行います。このプロセスを通じて、プロジェクトの全体像を深く理解し、共通の認識を持つことができます。
7-3.契約・プロジェクト開始:協業体制の構築
提案内容と費用に納得がいけば、契約を締結し、プロジェクトを開始します。 この段階では、委託する業務の範囲、成果物の定義、役割分担、コミュニケーションのルールなどを書面で明確にしておくことが不可欠です。
特に、円滑なプロジェクト推進のためには、定例会の頻度や報告フォーマット、機密情報の取り扱いなど、細かなルールを取り決めておくことが重要です。契約が完了したら、プロジェクトチームのキックオフミーティングを開き、関係者全員で目標とスケジュールを再確認し、協業体制を構築します。
08.【事例紹介】メンバーズ データアドベンチャーカンパニーはこうして課題を解決した
株式会社メンバーズの社内カンパニーであるデータアドベンチャーは、データ活用戦略の策定から施策の実行、さらには組織への内製化支援までを一気通貫で伴走するデータ活用コンサルティング・内製化支援パートナーです。 ここでは、同社がどのように企業の課題をデータと情熱で解決に導いているのか、実際の3つの事例を通して具体的に紹介します。
- ・顧客データ分析によるLTV(顧客生涯価値)の向上支援
- ・Webサイトの行動ログ解析によるUI/UX改善とCVR向上
- ・データ活用基盤の構築と分析組織の内製化支援
8-1.事例:顧客データ分析によるLTV(顧客生涯価値)の向上支援
オンライン学習プラットフォーム「Udemy」を運営するベネッセコーポレーションでは、事業の急成長に伴い、新規顧客獲得から既存顧客のリピート購入を促し、LTVを高めるフェーズへと移行していました。そこで同社は、専門家を常駐させ、顧客インサイトの深掘りを支援しました。
特に、講座レビューの自由回答を自然言語処理技術で分析し、これまで把握できなかった顧客の声を可視化しました。さらに、行動データとの相関分析から「アプリなどを使い隙間時間に学習するユーザーはリピート購入に繋がりやすい」という重要な知見を発見しました。
このデータに基づく発見は、社内でのアプリ活用促進の優先度を高める明確な根拠となり、LTV向上に向けた具体的な戦略立案に貢献しました。
8-2.事例:Webサイトの行動ログ解析によるUI/UX改善とCVR向上
KDDI株式会社では「auでんき」のWebサイトにおいて、複数のドメインにまたがってサービスが提供されていたため、ユーザーがサイトに流入してから申し込みを完了するまでの一連の行動データを正確に追跡できていないという課題がありました。これに対し同社は、Google Analyticsのクロスドメイン設定を実施してユーザー行動の分断を解消しました。
さらに、Googleデータポータル(現Looker Studio)でダッシュボードを構築し、リアルタイムでのデータ分析と関係者間での共有を可能にしました。この取り組みにより、ユーザーの離脱ポイントなどが明確になり、データに基づいたWebサイト改善のPDCAサイクルを回す体制が整いました。
結果として、部署全体のデータへの意識が向上し、より顧客視点でのサービス改善が進みました。
8-3.事例:データ活用基盤の構築と分析組織の内製化支援
タクシーアプリ『GO』を提供するGO株式会社では、事業成長に伴いデータ活用のニーズが急増する一方、複雑なデータ基盤を扱える専門人材(データエンジニア)の不足が深刻な課題でした。特に、一部で使われていた内製ETLツールはドキュメントが不十分で、メンテナンス性が低い状態でした。
この課題に対し、同社の常駐エンジニアは、属人化していたETLツールをGCPの標準サービスである「Dataform」へ移行するプロジェクトを主導しました。元のコードを1つずつ再現・検証し、移行作業の一部をPythonで自動化するなど、正確性と迅速性を両立させて移行を完遂しました。
これにより、データ基盤の運用効率と安定性が大幅に向上し、組織全体のデータ活用能力の底上げに成功しました。
詳細は弊社導入事例ページでご紹介しております https://www.dataadventure.co.jp/case_index/
09.データ分析の外注・会社選びに関するよくある質問(FAQ)
データ分析会社への依頼を検討する際、多くの企業や担当者の方が抱く疑問について、信頼できるソースをもとに分かりやすく解説します。目的や規模、地域、セキュリティへの不安を払拭し、安心してパートナー選びができるよう参考情報をまとめました。
9-1.Q. 中小企業でもデータ分析を依頼できますか?
はい、中小企業でも十分にデータ分析会社へ依頼し、経営改善や売上向上の成果を得ることが可能です。 クラウド型BIツールやAI搭載サービスの普及により、近年は低コスト・高効率化が進み、特定分野に強い中小企業向けサービスも続々登場しています。
政府のDX支援策や補助金、専門家派遣も活用でき、社内リソースが限られている場合でも外部プロの力で課題解決や高度な分析を実現した事例が多数報告されています。小規模・中小企業であっても、低予算でExcelや無料BIツール、クラウド型AI分析などを活用することが可能です。
9-2.Q. どのようなデータを準備すればよいですか?
準備すべきは業務課題や分析目的に合わせた自社保有のデータ(例:売上、顧客、在庫、Webアクセス、アンケートなど)で、種類や形式(CSV、Excel等)は事前に整理しておくことが推奨されます。 調査やアンケートなど自分で収集するプライマリデータだけでなく、業務システムに蓄積済みのセカンダリデータ、公開統計や外部ベンチマーク情報も活用できます。
データの種類や形式、収集方法、前処理(不要項目削除や形式統一)、ソース特定まで計画的に準備することで、分析品質と成果が向上します。
| データの種類 | 主な例 | 形式 |
|---|---|---|
| 数値データ | 売上、コスト、アクセス数 | CSV, Excel |
| カテゴリデータ | 顧客属性、商品区分 | Excel, データベース |
| テキストデータ | レビュー、アンケート回答 | テキストファイル, データベース |
9-3.Q. 地方の企業でも対応してもらえますか?
はい、地方企業でもデータ分析会社への依頼は可能です。 全国対応・リモート支援型の企業が増えており、地域特有の課題解決にも対応するサービスがあります。
例えば、Looker Studio等のクラウド型BIツールを使った地方市場向け分析、全国拠点による地域密着サポート、自治体によるデータ分析/調査支援など、地方発のDX事例が多数存在します。オンライン面談やリモート伴走形式が主流となり、物理的距離に関係なく専門的支援を受けることができます。
9-4.Q. 個人情報や機密データの取り扱いは安全ですか?
業界標準のセキュリティ対策(PマークやISMS認証取得企業、データ暗号化・アクセス管理など)を実施する会社に委託すれば、安全な体制で個人情報や機密データを扱えます。 具体的には、取り扱いルールの明文化、物理的および電子的なセキュリティの強化(アクセス権管理、入退室管理、暗号化)、日々のログ監視や従業員教育など多角的な対策が求められます。
情報管理専門業者へ外部委託することで、徹底した安全管理が可能です。不安な場合は契約前に体制内容、責任分担、コンプライアンス遵守状況を必ず確認してください。
まとめ:最適なデータ分析会社と共に、データドリブンな未来を共創しよう
データ分析会社は、業種・規模・地域を問わず、最新技術と専門知識を駆使して貴社の課題解決パートナーになり得ます。 分析目的に合わせてデータを適切に準備し、セキュリティや対応範囲もしっかり確認することで、「データドリブンな経営=データを根拠にした意思決定や課題解決」を誰でも始められる時代です。
中小企業・地方企業、初めての方でも安心のサポート体制やノウハウが蓄積されたプロ集団が多数活躍しています。今こそ、最適なデータ分析会社と共に、未来志向で競争力を高める経営の一歩を踏み出しましょう。
【1/27開催】より詳しい事例や展望をお話しします
記事ではお伝えしきれなかった生成AI活用の具体的な事例や、現場レベルの実装ポイントを解説する無料ウェビナーを開催します。当日は弊社執行役員兼一般社団法人Generative AI Japan理事の白井が登壇し、今後の展望含めリアルな知見をお話しします。ぜひお気軽にご視聴ください。

開催日 2026.01.27 (火) 11:00~12:00
AI導入でROIを生み出したいマネージャー・リーダー層や社内推進担当者必見。他社事例やトレンドを交え、業務実装のポイントを解説します。
データ活用でお悩みですか?まずは専門家にご相談ください
本記事で紹介したように、データ分析会社の選定には多くのポイントがあり、自社だけで最適なパートナーを見つけるのは簡単ではありません。株式会社メンバーズ メンバーズデータアドベンチャーカンパニーでは、データ活用戦略の策定から施策の実行、さらには組織への内製化支援までを一気通貫で伴走するデータ活用コンサルティング・内製化支援パートナーとして、多くの企業のDX推進を支援しています。
「何から始めればいいかわからない」「分析をビジネス成果に繋げたい」「データ活用を内製化したい」といったお悩みをお持ちでしたら、まずはお気軽にご相談ください。専門家が貴社の課題を丁寧にヒアリングし、最適な解決策をご提案します。
\ データ活用についてのご相談はメンバーズデータアドベンチャーまで /
\ 相談する前に資料を見たいという方はこちら /
▶こちらも要チェック
生成AIの普及に伴い、現在ではあらゆる企業でAI導入に向けて動き出しています。
しかし、「AIを導入したものの、期待した成果が出ない」という声も少なくありません。AIデータ分析を成功させる鍵は、目的に合わせた適切なプロセスを理解し、実行することにあります。本記事では、AIデータ分析を成功に導くための具体的なステップと、プロジェクトを始める前に知っておきたい「よくある落とし穴と解決策」を分かりやすく解説します。
▶目次
01.AIを使ったデータ分析とは?
01-1. AIデータ分析の定義
様々な解釈がありますが、ここでは「用途・目的に合ったAIを用いて、予測や分類などを行うデータ分析手法」と定義します。
中でも「用途・目的に合ったAIを用いて」という部分が非常に重要であり、必要に応じて用途・目的に即したAIを作るところから分析を始めなければなりません。
01-2. 従来の分析との違い
人間による手動分析も非常に数多くの手法があります。例えば、売上の前年比を算出して結果の裏には何の影響があったのか?を様々な数字から仮説を立ててみたり、数字をグラフにして可視化して要因分析してみたりなどが挙げられます。これらに共通する点は、人間が探索的に要因を分析している事。言わば 手動分析 です。
一方でAIは、入力されたデータから自律的に特徴を見つけ出し学習を行います。したがって、AIが結論を導き出した時には既に分析が完了しております。言わば 自動分析 です。
しかし、AIの思考プロセスは人間には見えにくく、「ブラックボックス」と化してしまうことがあります。そのため、ビジネスの現場では「予測精度は高いが、なぜその結論に至ったのか根拠が分からず、重要な意思決定に使いづらい」という課題が生じがちです。その中でも、一部のAIモデルでは、モデルの考えを解釈するための機能を持っているため、それらのモデルによるAIを用いる事でAIによる分析根拠を得る事ができます。これを XAI(説明可能なAI) と呼びます。XAIにより、ユーザーが 持ち合わせていない知見をAIから得る事ができる 場合もあります。
ただし、扱うデータやモデルが複雑な場合には分析根拠を解析するのが困難なため、XAIを実現できる範囲は限定的です。例えば扱うデータが画像や音声といった非構造データの場合、対応できるモデルも深層学習といった複雑なものになるため、分析根拠の解析は難しくなります。
01-3. AIデータ分析の種類
AIデータ分析の種類は、AIが扱う問題の種類から直結します。そのため、ここではAIが扱う問題の種類について説明します。AIが扱う問題にも様々な種類がありますが、代表的な3点を紹介します。
<予測(回帰問題)>
過去のデータから学習し、将来の数値を予測する手法 です。「来月の売上はいくらか?」「キャンペーンによる販売数は何個か?」といった問いに答えるために使われます。
【活用例】
- ・店舗ごとの売上高予測
- ・Webサイトのアクセス数予測
- ・商品の需要予測と在庫最適化
<分類(分類問題)>
データを特定のカテゴリに仕分ける手法 です。「この顧客はAとBのどちらのグループか?」「この取引は正常か異常か?」といった判断を行います。
【活用例】
- ・顧客がサービスを解約するかどうかの予測(チャーン予測)
- ・クレジットカードの不正利用検知
- ・迷惑メールフィルター
<クラスタリング(分類問題)>
明確な正解がないデータの中から、AIが自動的に似た性質を持つグループ(クラスター)を見つけ出す手法 です。人間が気づかなかった新たな顧客セグメントの発見などに繋がります。
【活用例】
- ・顧客の購買傾向に基づいたセグメンテーション
- ・アンケート結果のグループ分けによるインサイト抽出
- ・類似した特徴を持つ製品のグルーピング
02.AIデータ分析を成功へ導く3つの実践ステップとAIの役割
本章では、AIデータ分析を成功に導くための分析過程を、3つのステップに分けて説明します。
02-1. ステップ1:分析目的の明確化とデータ準備
まずはじめに、AIを用いて「何を分析したいのか」「何を解決したいのか」「どのような成果を得たいのか」という目的 を明確化します。ここが曖昧なまま進むと、分析そのものが目的化してしまい、ビジネス価値のない結果に終わる可能性が高まります。分析目的が決まったら、目的に合ったデータの収集を行う必要があります。データが不足している場合には外部データから調達する必要も生まれます。
どのようなデータが必要かについては目的によって大きく異なるため一概には言えませんが、ここではクレジットカードの自動審査を目的とした例を挙げます。目的は「審査業務のAI移管」とします。これを実現するAIを作るために必要なデータは、審査を行うためのデータに加え、審査してOKな会員とNGな会員を区別するためのフラグです。
過去の実績から、実際に与信した 会員の申込情報 (年齢・年収・業種・役職など)と、その会員が 貸倒したかどうか を集計して1つのデータとしてまとめます。これで、与信してOKな会員とNGな会員の情報を学習させるためのデータセットがひとまず揃います。
一方で、与信するかどうかを判断するために必要な材料として、申込情報だけでは不十分ではないかという懸念点もあります。このような場合には 外部データの調達 を考えます。具体的には、信用情報機関からの外部信用情報を調達したり、法人カードならば東京商工リサーチなど企業情報を扱っている企業から財務情報・企業評価などを調達したりします。
02-2. ステップ2:AIモデルの構築と学習
次にAIモデルの選択と学習を行います。これは、データに潜むパターンをAIに学ばせる、データ分析の中核となるプロセスです。
まずは、目的に応じて最適なAIモデル(アルゴリズム)を選択します。例えば、不正利用検知なら「分類」モデル、売上予測なら「予測(回帰)」モデルといった形です。アルゴリズムには決定木、ランダムフォレスト、ディープラーニングなど様々な種類があり、データの特性や求める精度に応じて選び分ける必要があります。AIの分析根拠を解析したい場合には、説明可能性の高いXAIを実現できるモデルを用いるのも1つの選択肢です。
モデルを選択したら、早速用意したデータセットを用いて学習を行いたい所ですが、学習の前にデータセットを学習に適した形に加工する必要があります。主に行う加工は以下のものがあり、総じて特徴量エンジニアリングと呼びます。
- ・欠損値の処理
- ・学習に不要な変数の削除
- ・文字型変数の数値変換
- ・教師データの分別
- ・全体データの学習用データと評価用データへの分割
特徴量エンジニアリングが完了したら、AIモデルの学習(機械学習)を行います。機械学習の際は学習用データのみ使用し、こちらがモデルに対して行う事は基本的にはありません。AIが自動的に学習データと教師データからパターンを分析・学習していくプロセスになります。
02-3. ステップ3:AIモデルの評価と解釈
AIモデルの学習が完了したら、その性能が実用に足るものかを確認する「評価」と、AIがどのような根拠で判断しているかを理解する「解釈」を行います。
学習に使っていない未知の評価用データをモデルに推論させてみて、AIの性能として問題無いか、客観的な評価指標を用いて確かめます。次に、AIの判断根拠を可視化・解釈します。例えば、審査モデルであれば、「年収の高さが承認に強く影響している」「過去の延滞歴が否決の大きな要因になっている」といった根拠をSHAPなどの手法で明らかにします。
判断材料としては簡単なケースを挙げましたが、これによりAIの判断がビジネス上の知見と合致しているかを確認でき、人間では気づかなかった新たなインサイトを得られることもあります。
02-4. ステップ4:施策への導入と運用
モデルの有効性が確認できたら、いよいよ実際の業務へ導入し、運用していくステップに移ります。
いきなり全面的に導入するのではなく、まずは限定的な範囲でスモールスタートするのが成功の鍵 です。例えば、「このAI審査モデルを導入すると、全体の何%が自動で承認判定になるか」といったシミュレーションを行い、ビジネスへの影響を事前に予測します。
ただし、作成したモデルを初めて活用するようなプロジェクトはPoCの段階である事が多い点 と、実際に施策を行う時はシミュレーション結果よりやや精度が落ちる事も多い ため、あくまで参考値として扱う事を推奨します。
シミュレーションが完了したら、実際に自動審査を行います。シミュレーションと同じ手順で、審査用データを特徴量エンジニアリングしてAIに入力する事で自動審査が行われます。仮にAIが、人間と同水準のレベルで審査を行うことができた場合、当初の目的である「審査業務のAI移管」は達成となります。
また、モデルは一度作ったら完成!という事は無く、市場環境や顧客の行動は常に変化するため、継続的に再学習など調整を行う必要があります。毎月毎月学習を行う必要は無いですが、精度が落ちてきた場合は再度学習を行ってパフォーマンスを維持できるようにするのも大切です。
03.AIデータ分析でつまずかない!よくある落とし穴と解決策
多くの企業がAIデータ分析に期待を寄せる一方で、プロジェクトが思うように進まず、途中で頓挫してしまうケースも少なくありません。成功を阻む「落とし穴」は、ある程度パターン化されています。この章では、AIデータ分析プロジェクトで陥りがちな4つの代表的な失敗パターンと、それらを乗り越えるための具体的な解決策を解説します。
03-1. データ不足やデータ品質の問題
良いモデルを作成するためには、十分なデータ量を確保するのが重要です。しかし、ただ量を集めれば良いという訳ではありません。データの質も問題無いか確認する必要があります。よくある例としては以下の通りです。
- ・季節性を無視したデータ収集
例:売上予測なのに夏の3ヶ月分だけを収集→冬の需要が読めないモデルに。最低でも1年通したデータを収集する。 - ・学習データと本番データでカラム定義やカテゴリが違う
例:学習時では「性別:男性/女性」なのに、本番では「性別:Male/Female」になっている。AIにとっては未知の値である。必ずカラム定義は揃える。 - ・極端に少ない教師データ
例:自動審査モデルを作りたいのに、否決データが全体の1%しかなく、モデルがほぼ応諾と予測するだけになってしまう。即ち、学習データが応諾のものばかりなので「あるもの全て応諾だ」と勘違いしやすくなる状態に陥りやすい。極力、教師データの正例/負例バランスは偏りすぎないように考慮する。
【解決策】
AI導入の前に、まずは自社のデータを整備し、いつでも分析に使える状態にする「データ基盤の構築」を優先しましょう。不足しているデータは外部から購入したり、計画的に収集したりする戦略が必要です。また、データの入力ルールを定め、全社で徹底するデータガバナンスの確立も不可欠です。
03-2. AIモデルがブラックボックス化してしまう
AIとは基本的に入力から出力までの過程が見えないブラックボックスなものです。AI、特にディープラーニングのような複雑なモデルは、人間が理解できないレベルで無数の計算を行い結論を出すため、なぜその結論に至ったのかを論理的に説明することが困難だからです。
その結果、「予測精度は95%と高いが、なぜこの顧客が『解約する』と予測されたのか根拠が分からないため、具体的な対策が打てない」といった事態に陥ります。重要な経営判断や顧客への説明責任が求められる場面で、根拠の不明なAIの予測を鵜呑みにすることはできません。
【解決策】
分析の目的に応じて、解釈性の高いAIモデルを選択することが重要です。例えば、勾配ブースティングモデルはSHAPのようなXAI手法と組み合わせることで、分析根拠を事後的に解析できるため有力な選択肢の1つです。また、AIの専門家が分析結果をビジネスの視点で分かりやすく翻訳し、現場担当者との橋渡し役を担うことも解決策の1つとなります。
03-3. 社内にAIデータ分析の専門人材がいない
AIデータ分析プロジェクトを推進するには、 ビジネス知識、ITスキル、統計学の知識を併せ持つ専門人材が不可欠 です。
データサイエンティストやAIエンジニアと呼ばれるこれらの人材は、専門性が非常に高く、多くの企業で不足しているのが現状です。専門知識がないままプロジェクトを進めようとすると、適切な分析手法を選べなかったり、出てきた結果を正しく評価できなかったりと、多くの問題に直面します。
【解決策】
AIデータ分析の学習コストは非常に高いため、即座にAIデータ分析を取り入れたい場合は外部のデータ活用人材を活用するのが現実的です。加えて、データ活用人材からノウハウを吸収することで、社内のデータサイエンティストやAIエンジニアの育成も効果的に行うことが期待できます。中長期的には、社内研修やリスキリングを通じて自社の人材を育成する計画を立てることが重要になります。
弊社では、AIモデルの開発をはじめとしたデータ活用支援から内製化支援まで幅広くサポートしております。
03-4. 分析結果が施策に繋がらない(PoC止まり)
AIモデルを構築し、高い精度が出ることを確認したものの、 実際の業務改善や売上向上に繋がらず、実証実験(PoC)の段階で終わってしまう「PoC止まり」は、多くの企業が直面する課題 です。
この問題の根底にあるのは、プロジェクトの目的設定の誤りです。分析の目的を「AIモデルを作ること」自体に置いてしまうと、「モデルはできたが、これをどうビジネスに活かせばいいのかわからない」という状況に陥ります。
AIデータ分析はあくまでビジネス課題を解決するための「手段」であり、目的ではありません。
【解決策】
AIデータ分析を開始する前に目的を明確化する事が最も重要です。ゴールを「AI分析する事」にするのではなく、「AI分析して得た結果を施策に繋げる事」まで考えて分析を行いましょう。また、PoCの段階では施策をスモールスタートにして小さな成功体験を重ねながら、AI活用のスケールを広げていく事も有効です。
04.AIを使ったデータ分析に関するよくある質問(FAQ)
Q1. 自社データがない、または少ない場合でもAIデータ分析は可能ですか?
A. ゼロからのスタートは難しいですが、オープンデータや外部データとの組み合わせ、あるいは少量データからの学習(転移学習など)で始める方法もあります。ただし、精度を高めるには十分なデータ量が理想です。データ収集戦略を練り、将来を見据えて計画的にデータ収集を行う事から始めるのも立派な手段の1つです。
Q2. AIデータ分析の「精度」はどのように評価・改善すれば良いですか?
A. 精度は「ビジネス目的と紐づいた指標」で評価し、「継続的な改善サイクル」を回すことが不可欠です。 精度評価には主に2種類の指標があります。モデルとしての性能を測る評価指標(例:AUCや適合率)と、ビジネス目的と紐づいた指標(例:審査の応諾割合、否決割合)です。双方の指標の良さは比例する事が多いですが、モデル作成過程では前者を、シミュレーション時や施策結果からモデルを見る時は後者を使います。基本的には、ビジネス的に立てた目標数値をモデルが達成できなかった時に改善を検討する流れになります。改善の際には、評価指標の目標数値を達成するように調整すれば問題ありません。
まとめ
本記事では、AIデータ活用を成功させるためのAI作成ステップについて紹介しました。やや技術的な部分が多くなってしまいましたが、これからAI導入を検討している方も、一体AIはどのように作られるのか?どのようなデータが必要なのか?といった事は知っておく必要があります。
中でも「AIを用いた分析をする事」を目的にするのでは無く、「AIを用いた分析を使って何をどう成し遂げるのか」までを目的にして、入口から出口までを一気通貫で考える事が重要です。そこまで考えた上でようやく必要なAIを設計する事ができるのです。
\ データ活用についてのご相談はメンバーズデータアドベンチャーまで /
\ 相談する前に資料を見たいという方はこちら /